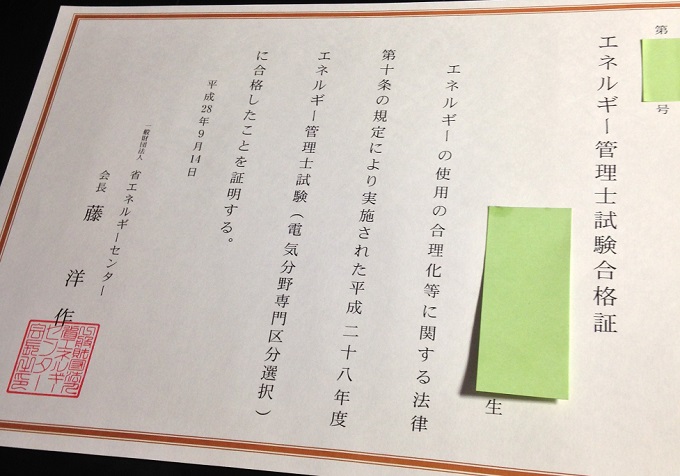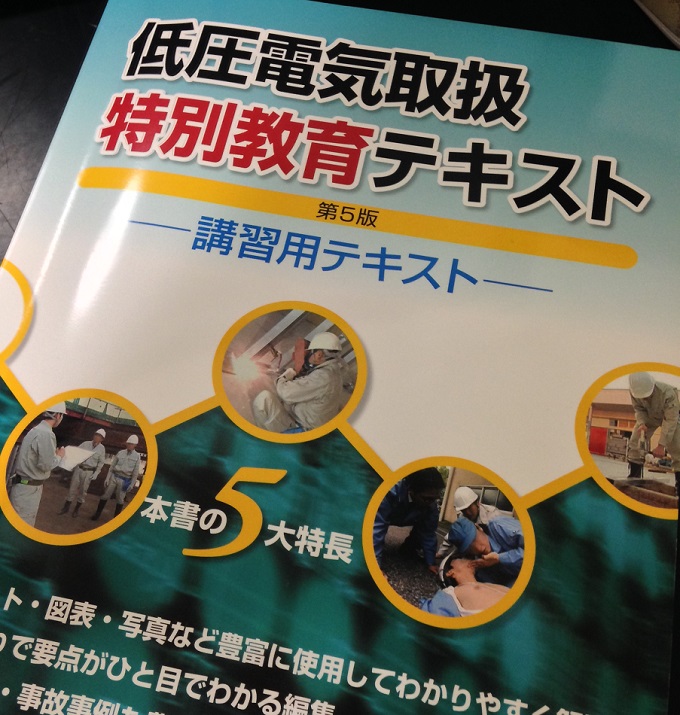消防設備士4類は、消防設備士のなかでもっともメジャーな分野です。
普段は意識しませんが、感知器は生活のいたるところにあります。この記事では、消防設備士4類の難易度、参考書、勉強法、管理人の体験談等を紹介していきます。
【受験概要】

【資格名称】甲種第4類消防設備士
【受験年度】平成28年度
【試験点数】
筆記試験:筆記全体(97%) ≪法令(100%) 基礎知識(90%) 機能・構造(100%)≫
実技試験:実技全体(85%)
消防設備士4類は、自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備が主な分野になります。建物の天井についている感知器(下の写真)くらいは、多くの人が見たことがあると思います。

勉強時間
勉強期間は106日間、勉強時間は45時間13分。
消防設備士は乙種4類に合格済みでした。
しかし、合格後から数年間経過しており、ほとんど何も覚えていませんでした。ただ、現在は消防設備士を連続で受験しており、法令の共通部分の知識だけはありました。
4類の勉強範囲はなかなか広いです。
実技試験の製図もいろいろなパターンがあります。すべて対策しようとすると、かなり勉強時間が必要だと思います。管理人は、出題される可能性が低そうな炎感知器の製図などは、そこまで対策しませんでした。
受験時の主な所持資格:消防設備士乙4、甲5、電験3種
勉強時間の目安
勉強時間の目安は、資格勉強になれていない人で50時間~100時間くらい。電気工事士や消防設備士などの関連資格の合格者で20時間~50時間くらいでしょうか。
以上は、甲種4類の勉強時間です。製図のない乙種4類は、もう少し短い時間で大丈夫です。
消防設備士試験は、一夜漬けでは合格できない試験です。知識のある人でも、10時間程度の勉強は必要です。ただ、しっかり勉強時間を取れば、必ず合格できる試験です。150時間~200時間程度勉強すれば、誰でも受かる試験だと思います。
消防設備士は暗記型の試験なので、1問1問の演習速度が速いです。繰り返し参考書を勉強しても、そこまで時間はかからないと思います。
マークシート式の筆記試験以外にも、記述式の実技試験があります。理解が浅いと、実技試験で点数が足りなくなります。勉強時間の多くを実技試験に使う必要があります。
消防設備士甲4の受験資格
消防設備士は甲種からは、受験資格が必要です。受験資格の詳細はこちらになります。今回の甲4類の受験では、電気工事士の免状で受験申請しました。
電気工事士などの科目免除
| 主な科目免除表 | 電気工事士 | 電気主任技術者 | 消防設備士 | |
| 基礎的知識 | 電気 | ○ | ○ | |
| 消防関係法令 | 共通 | ○ | ||
| 4類 | ||||
| 構造・機能・ 工事・整備 | 電気 | ○ | ○ | |
| 規格 | ||||
| 実技試験 | 鑑別問1 | ○ | ||
電気工事士の資格は、消防設備士甲種の受験資格ですが、科目免除の要件にもなります。電気工事士で科目免除を申請すると、基礎的知識の「電気分野」、構造、機能、整備及び工事の「電気分野」、実技試験の鑑別問題の問1が免除されます。
電気工事士免除は、いろいろとお得な特典がてんこ盛りのイメージがあります。しかし、管理人的に言うと、これは罠です。
第2種電気工事士で計算問題が苦手だった人以外は、免除を利用しない方が良いというのが管理人の意見です。
特に、実技試験の鑑別問題が免除されてしまうのは痛い。今のところ、鑑別の問1は比較的簡単な場合が多いです(平成28年現在)。筆記試験の電気分野も電工2種に合格できた人ならば、簡単に感じるはずです。管理人は、電気分野はほぼ無勉強でした。
電験(電気主任技術者)の免除ですと、鑑別が免除されないので意外とお得かなと思いました。
消防設備士の免除
他の類の消防設備士を取得している方は、消防設備士の科目免除が利用できます。消防設備士の科目免除を利用すると、消防関係法令の「共通分野」が免除されます。管理人的には、この免除は使ってもどちらでも良いと思います。
他の類の消防設備士を受験したばかりで知識が残っているなら、この分野は得点源にできます。昔に他の類を受験して知識が残っていないなら、科目免除を検討しても良いと思います。
筆記試験は6割取れば合格です。意外とこの6割のラインは簡単に越えられます。そう考えると、勉強量を減らすために、消防設備士の免除は使った方が良いのかもしれません。
【難易度】
甲種4類:★★★★☆☆☆☆☆☆ (4/10 普通下位)
乙種4類:★★★☆☆☆☆☆☆☆ (3/10 やや易)
過去の合格率
| 受験年度 | 甲4合格率 | 乙4合格率 |
| 平成24年 | 28.4% | 40.6% |
| 平成25年 | 33.5% | 38.1% |
| 平成26年 | 35.0% | 34.0% |
| 平成27年 | 34.0% | 33.7% |
| 平成28年 | 32.1% | 32.9% |
| 平成29年 | 30.8% | 34.0% |
| 平成30年 | 32.4% | 32.4% |
| 令和元年 | 32.5% | 33.6% |
| 令和2年 | 37.4% | 36.8% |
消防設備士4類は、範囲は広いのですが、難易度はそれほど高くないと思います。同じ消防設備士だと、メジャーなところで乙6と乙4は同じくらいの難易度だと思います。4類は、乙種から甲種に変わっても、そこまで難易度はあがらない印象です。
合格率は甲種4類が3割前後、乙種4類も3割中盤で安定しています。試験の難易度自体は、昔とそれほど変わっていないと思われます。
甲種は受験資格があるので受験者の質が乙種より高いのでしょう。それで甲種も乙種も同じような合格率だと思われます。
受験者数は、おおむね増加傾向です。
管理人は、第3種電気主任技術者持ちなので、電気系の資格は比較的得意です。消防設備士甲種4類に関しては、かなり相性の良い試験でした。
【受験動機】
消防設備士をコンプリートするための受験です。感知器はいたるところで見かけますが、仕事で使うことはありません。
ただ、消防設備士4類を所持していると、感知器が鳴った時、どの種類の感知器がどうして作動したのか分かるようになります。非常にためになる知識です。
防災屋から、ビル管理、設計、警備員まで幅広い職種で役に立つ資格です。
消防設備士の免状所持者は、資格を取得すると5年に1度講習を受講する必要があります(最初の講習は、資格取得後最初の4月1日から2年以内)。講習は全部で4つあります。
| 免状の種類 | 講習の種類 |
| 甲種特類 | 特殊消防用設備等 |
| 1・2・3類 | 消火設備 |
| 4・7類 | 警報設備 |
| 5・6類 | 避難設備・消火器 |
私はすでに甲種4類、甲種5類、乙種6類を所持しているので、警報設備と避難設備・消火器の二つの講習は受講する必要があります。この場合、1類~3類のいずれかの免状を取得してしまうと、あらたに消火設備講習も受講しなくてはなりません。
どちらにしても、甲種1類~3類も受験します。
そこで気になるのが講習の受講義務です。
講習の受講は、4月1日が区切りです。なので、次の年の4月1日まで1類~3類を受験しなければ、あらたに受講義務が発生する消火設備講習を先延ばしにできます。1類~3類を受験しても落ちてしまえば、受講義務もなにもありませんが(笑)
資格を使わない方は、講習を受けなくても多分大丈夫です。試験問題では、講習を受けないと免状が取り消しになるとか言ってたりしますがねw
【参考書】
以下の記事では、消防設備士4類の参考書をまとめてあります。

【勉強方法】
筆記試験
消防設備士の筆記試験は、全体的に難化傾向かもしれません。甲種5類を受験した時にも、筆記試験が意外と難しいなと感じました。管理人の甲種4類の筆記試験の点数は高いのですが、意外と分からない問題が多かったです。
筆記の勉強は工藤本で余裕ですね。ゴロ合わせが非常に使いやすいと思います。
電気工事士免除や消防設備士免除は使うかどうか悩むところです。電気系の計算は、覚えれば簡単に解けます。計算がどうしても苦手な人以外は簡単なはずです。
消防関係法令の共通分野も意外とパターンが決まっています。工藤本を読みこまなくても、問題演習を繰り返せば、6割以上取れると思います。
今は公論出版の問題集の方がおすすめかもしれません。
公論出版は非公開なはずの過去問をそのまま掲載しています。
実技試験
実技試験は、某巨大掲示板の過去ログでの勉強がおすすめです。こちらのサイトで「消防設備士」と検索して、4類の過去ログをすべて読みましょう。非常に役に立つ情報が多いです。
平成28年度は、あまり嫌らしい製図問題が出題されていないようです。変電室に差動スポット試験器を使うというのが、最近のハヤリかもしれません。
今の難易度ですと、製図専用の参考書を買わなくても十分勝負になるかもしれません。管理人の意見としては、難易度があがった時のために、製図の本を用意した方が良いと思います。
製図勉強のワンポイント
消防設備士の製図を勉強する際、トレーシングペーパーを使うと勉強の効率があがります。管理人の製図の勉強法は、以下の記事にまとめてあります。

【試験本番】
試験本番に出題された問題などを以下の記事にまとめてあります。

【合格後】
仕事では使わないので、資格マニアとしての受験です。甲5類→甲4類→乙7類と受験しました。
消防設備士4類を取得すると、お店などの天井についている感知器の種類が分かるようになります。天井を見るのも楽しいですよ。
本職以外の警備員やビル管理などでは、重要度の高い資格かもしれません。別に所持していなくても仕事はできますが、消防設備士4類と6類の知識は頭に入れておくのがおすすめです。
【最後に】
消防設備士4類と6類の受験は、かなりおすすめです。非常にためになる知識が多いので、仕事で使わない人も4類と6類を受験してみると良いかもしれません。