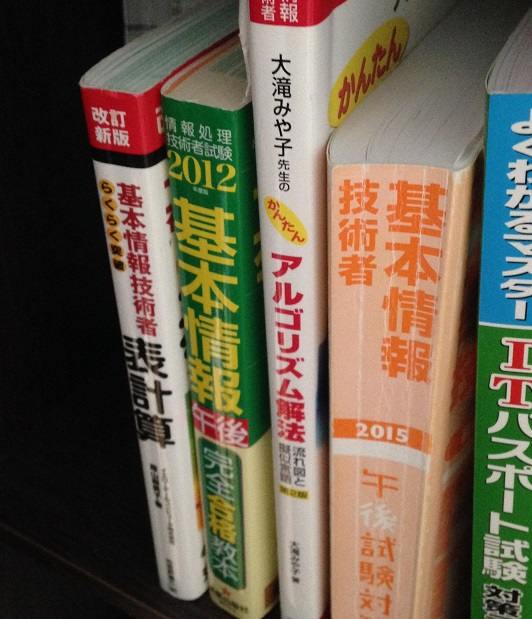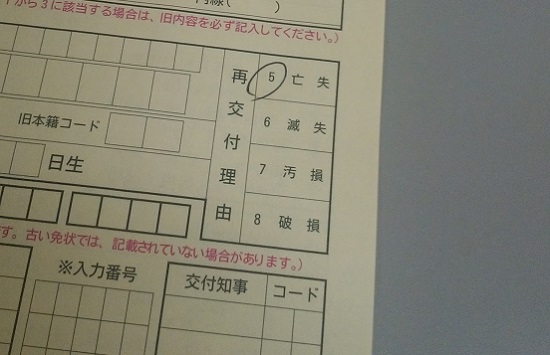未経験者が設備管理(ビルメン)に就職しようとする時、まずは資格の取得を考えると思います。この記事では、設備管理(ビルメン)未経験者がどのような順番で設備系資格を取得していくべきかを考えてみようと思います。

結論としてはどの資格から受験しても構わない
結論から言うと、未経験者が設備系資格を目指す場合、どの資格から受験しても構わないと思います。
いきなり記事が終わってしまいそうなので、もう少し深く考えてみようと思います。
未経験者が目指すべき設備系資格
未経験者が設備系の資格を目指す場合、まずビルメン4点セットを受験しようと考える人が多いかもしれません。

ネット上でも、「4点セットを取ればビルメンになれる」なんて意見が多いです。しかし、実際は資格より若さの方が大事です。当たり前のことですが、若いうちは気づきにくいかもしれません。
4点セットの内訳は、第2種電気工事士(電工2種)、乙種4類危険物取扱者(危険物乙4)、2級ボイラー技士(2級ボイラー)、第3種冷凍機械責任者(冷凍3種)の4つの資格です。
当然ですが、4点セット以外にも設備系の資格はたくさんあります。そのなかでも、初級者が目指すべき資格は、消防設備士甲(乙)種4類と消防設備士乙種6類です。
消防設備士の4類と6類は、消防設備士試験のなかでも需要が高い資格です。
消防設備士の4類は、感知器などの勉強をします。感知器は、建物の天井などについています。住宅にも設置することが法律で義務付けられています。ご自宅の天井にもそれらしきものがあるかもしれません。

消防設備士の6類は、消火器の勉強がメインです。
消防設備士は、甲と乙の試験種類があります。甲の方が難しくて、乙の方が少し簡単です。4類には甲と乙があるのですが、6類には乙しかありません。

未経験者が設備系資格を目指す場合、4点セットと消防設備士4類と6類の全部で6つの資格がメインになるかと思います。
ビルメンを目指すための職業訓練校などでも、この6つの資格を受験する人が多いです。
分野による設備系資格の分類
上にあげた6つの資格を分野ごとに分類してみます。
電気系資格
初級の電気系資格は、第2種電気工事士(電工2種)です。上位資格に、第1種電気工事士(電工1種)があります。

電工1種は誰でも受験できるのですが、合格しても実務経験がないと資格になりません。電工1種は電工2種より少し難しいですが、電工2種の合格者なら手が届く範囲だと思います。
さらに上位の電気系資格は、電気主任技術者(電験)という資格です。電気主任技術者は、実務経験が必要ありません。しかし、電気工事士とは比べものにならないほど難しいです。

電気系の資格は、現場の入札で必要資格になっていることが多いです。どの資格も非常に重要です。何の資格を取るか迷ったら、とりあえず電気系の資格を勉強してみるのもアリです。
熱源系資格
初級の熱源系資格は、2級ボイラー技士(2級ボイラー)と第3種冷凍機械責任者(冷凍3種)の二つです。
熱源というと分かりにくいかもしれません。要は、ボイラーや冷凍機で空気や水などを暖かくしたり冷たくしたりするということです。ご自宅のエアコンも同じような仕組みです。


2級ボイラーの上位資格は、1級ボイラー技士(1級ボイラー)です。1級ボイラーは受験資格が必要です。2級ボイラーを取得した人なら誰でも受験できますが、合格しても実務経験がないと資格になりません。
1級ボイラーの難易度は、2級ボイラーとほとんど差がありません。1級の方が細かい知識を聞かれますが、1級も過去問の繰り返しで合格できる難易度です。
1級ボイラーは、2級ボイラーに合格後、知識が残ってるうちに試験合格だけしてしまう人もいます。合格したという事実は消えませんので、後で実務経験を積めば資格を取得できます。
さらに上位には特級ボイラー技士(特級ボイラー)があります。特級ボイラーは、受験資格や難易度の関係で非常に取得しにくいです。
冷凍3種の上位資格は、第2種冷凍機械責任者(冷凍2種)です。さらに上位の資格は、第1種冷凍機械責任者(冷凍1種)です。
冷凍機械責任者の資格は最上位の1種でも、受験資格や実務経験が必要ありません。

冷凍試験は、受験資格がないということもあって、比較的簡単に最上位の冷凍1種まで取得できます。上位の試験の難易度もそこまで高くありません。
また、冷凍試験には講習制度があります。講習を受講して検定試験に合格すると、本試験が半分以上免除になります。この制度を使うと、比較的簡単に上位資格に合格できます。
化学系資格
初級の化学系資格は、乙種4類危険物取扱者(危険物乙4)です。上位資格は、甲種危険物取扱者(危険物甲種)です。
危険物乙4では、石油などの設備系現場でよく使われる燃料の勉強がメインです。4類以外にも危険物の種類があるのですが、目にする機会は少ないかもしれません。

危険物甲種の受験資格は、少し複雑です。学歴や実務経験で受験できる人もいます。高卒で実務未経験の人でも甲種を受験できる方法があります。
危険物取扱者試験は、1類~6類まであります。そのなかの数種類の乙種(乙種1類など)を取得すると、甲種を受験できるようになります。
危険物甲種は、危険物乙4よりも難しいです。ただ、危険物乙4に合格できた人なら努力次第で合格できる資格だと思います。

消防系資格
初級の消防系資格は、消防設備士甲(乙)種4類と消防設備士乙種6類です。上位資格が甲種で下位資格が乙種という分類ですが、甲種と乙種の難易度にはそこまで差がありません。

消防設備士甲種を受験する場合に問題となるのは、難易度ではなく受験資格です。王道の受験資格は、第2種電気工事士の資格です。甲種がある4類に関しては、第2種電気工事士合格後に甲種から受験する人も多いです。
4類と6類以外にも1類もそこそこ受験者数が多いです。
資格の分野による受験優先順位はない
このように設備系資格にはさまざまな分野があります。それぞれの勉強内容が重複している資格も多いです。しかし、どの資格から受験すべきというセオリーはありません。資格Aを勉強していないと、資格Bの内容が分かりにくいというケースが少ないからです。
ここに挙げた6つの資格は、すべて初級資格です。それぞれの分野での基礎を勉強する資格です。基礎レベルの勉強なので、どの資格から勉強しても勉強につまることはないはずです。
分野による受験優先順位はないのですが、二つだけ注意点があります。
消防設備士4類の受験は、第2種電気工事士に合格した後がおすすめです。
第2種電気工事士を取得していれば、甲種から受験できます。また、甲種4類には電気分野の問題があります。電工2種を勉強した後ならば、4類の電気系の勉強がスムーズに進みます。
電気工事士の資格を持っていると、消防設備士4類の電気系分野の問題を免除できます。しかし、消防設備士の電気系分野の問題は、比較的簡単な問題が多いです。免除するかどうか決めるのは、消防設備士の参考書に目を通してからでも遅くありません。
もう1点は、冷凍3種の受験は、ある程度資格勉強に慣れた後がおすすめです。
冷凍3種は、非常に癖のある試験です。一発目の設備系資格の受験に冷凍3種を持ってくると、人によってはかなり苦労することになります。
設備系資格の受験優先順位は分野によってではなく、受験日程によって決めるべきです。
日程による設備系資格の分類
設備系資格を受験できる時期はそれぞれ違います。
1年に1度しか受験できない資格
1年に数度しか受験できない資格は、電工2種と冷凍3種です。
第2種電気工事士
電工2種の受験スケジュールは、上期と下期があります。それぞれ6月・7月と10月・12月に試験が開催されます。
試験には、筆記試験と技能試験があります。上期ならば、6月の筆記試験に合格した人だけが、7月の技能試験を受験できます。試験スケジュールの詳細はこちら。
受験時期は上期と下期があります。平成30年度からは、上期と下期の両方を受験することが可能になりました。
電工2種は、設備系資格のメインともいえる資格です。電工2種の受験日程を軸にして、他の資格試験の受験スケジュールを決めるべきだと思います。
第3種冷凍機械責任者
冷凍3種は1年に1度しか受験できない資格です。試験開催月は11月上旬です。試験スケジュールの詳細はこちら。
冷凍3種は、受験時期が合えば受験すべき資格です。1年に1度の試験ですが、電工2種のように必須に近い資格ではありません。1年に何度も受験できる資格よりは優先した方が良いといったところです。
1年に何度も受験できる資格
危険物乙4、消防設備士4類 or 6類、2級ボイラーは1年に何度も受験できる資格です。
危険物取扱者と消防設備士
危険物と消防設備士は、試験実施団体が同じです。
危険物の試験スケジュールの詳細はこちら。
消防設備士の試験スケジュールの詳細はこちら。
受験時期が上期と下期に分かれています。また、都道府県ごとに試験が開催される時期が違います。隣の都道府県の試験日程の方が都合が良いのであれば、遠征して受験できます。管理人は埼玉県在住ですが、東京都で開催される消防設備士試験を受験したりします。
2級ボイラー技士
2級ボイラー試験は、一月に最低1度は開催されます。2級ボイラーの試験スケジュールの詳細はこちら。
危険物や消防設備士と違って、2級ボイラー試験はすべての都道府県で試験が開催されるわけではありません。
北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州と地方ごとに支部が一つあります。その支部で毎月試験が行われています。
関東の支部は千葉にあります。東京在住の人も、2級ボイラーを受験するために隣の千葉県まで遠征する必要があります。
ただ、年に1度出張試験があります。その時期に合えば、自分が住んでいる都道府県で試験を受験できます。出張試験の詳細はこちら。
設備系資格は日程によって受験優先順位を決める
設備系資格を受験する場合は、まずは受験回数に制限がある電工2種と冷凍3種の日程を優先しましょう。特に実際の現場で重要になる電工2種を中心に考えることをおすすめします。
そこに1年に何度も受験できる資格を組み合わせて受験しましょう。受験遠征を考えてもいいと思いますが、お金や時間がない人は無理して遠征する必要はないと思います。
最後に
どこまで行っても、資格は資格です。すごい人が資格を持っているケースは多いですが、資格を持っているから仕事ができるかというと違います。
資格マニアである管理人は、資格だけでは意味がないと感じることも多いです。資格はある程度は必要ですが、とにかくたくさん資格があればいいというものではありません。
就職活動でもたくさん資格を持っているから、合格するというわけでもありません。4点セットをすべて取ってからではなく、少し資格を取得してすぐに就職活動をした方が結果が良い場合が多いはずです。
資格の取得は計画的に。