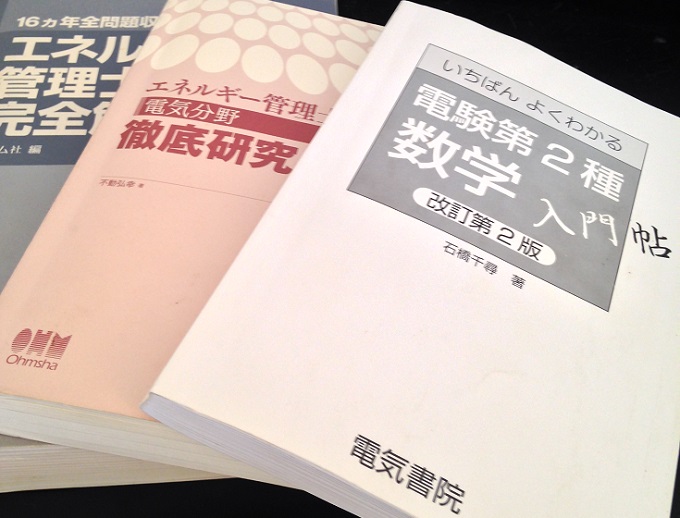平成27年に危険物乙1、乙3、乙5と続けて合格しました。その知識を忘れないうちにと思い、同年に危険物甲種の受験に踏み切りました。この記事では、危険物甲種の難易度、参考書、勉強方法、管理人の体験談等を紹介していきます。
【受験概要】
【資格名称】甲種 危険物取扱者
【受験年度】平成27年度
【試験点数】法令 (66.6%) 物理・化学 (60%) 性質・消火 (80%)
ギリギリ合格です(笑)。受験後は落ちたかもと思いました。危険物や消防設備士試験は問題用紙が持ち帰れないので、自己採点ができません。経験上、合格か不合格か分からない時は大抵合格しています。
物理・化学には自信があり、性質・消火には自信がありませんでした。自信がない性質・消火を集中的に勉強しました。手を抜いた物理・化学の得点は伸びず、性質・消火が最高得点になりました。
勉強時間
勉強期間は60日間、勉強時間は39時間29分。
乙種4類は数年前の合格です。甲種の受験と同年に乙種1類、3類、5類と受験しました。4類以外の乙種は科目免除での受験だったので、法令や物理・化学はほぼゼロからの勉強でした。性質・消火も2類と6類は知識ゼロの状態で勉強を開始しました。
受験時の主な所持資格:危険物乙1、乙3、乙4、乙5
危険物甲種の受験資格
甲種を受験するためには、受験資格が必要です。私のような普通科高校卒で危険物取扱の実務がない場合は、最低限4種類の危険物乙種が必要です。
資格マニア的な受験パターンですと、乙種を全類合格してから甲種を受験する人が多いかもしれません。管理人は、甲種受験に必要な乙種を最低限の4種類合格して甲種を受験しました。
乙2類と乙6類の知識がない状態で勉強を開始しました。その分少し勉強時間が多くなりました。お金と時間に余裕があれば、乙種をコンプリートしてから受験すると楽かもしれません。
| 甲種受験に必要な資格 | 管理人の場合 |
| 危険物乙種1類または6類 | 乙種1類を平成27年度に受験 |
| 危険物乙種2類または4類 | 乙種4類を平成24年度に取得済み |
| 危険物乙種3類 | 乙種3類を平成27年度に受験 |
| 危険物乙種5類 | 乙種5類を平成27年度に受験 |
【難易度】
★★★★★☆☆☆☆☆ (5/10 普通中位)
過去の合格率(平成28年1月まで)
| 受験年度 | 合格率 |
| 平成23年 | 33.1% |
| 平成24年 | 32.8% |
| 平成25年 | 33.2% |
| 平成26年 | 32.8% |
| 平成27年 | 31.7% |
| 平成28年 | 33.5% |
| 平成29年 | 37.3% |
| 平成30年 | 39.8% |
| 令和元年 | 39.6% |
| 令和2年 | 44.1% |
危険物乙種4類の合格率も甲種の合格率も同じ30%~40%前後です。合格率だけで比較すると乙4と同程度ですが、甲種は受験資格が厳しいので受験者の質が高くなります。その中での合格率ですので、簡単な資格ではないと思います。
危険物甲種の難関は物理・化学だと思います。
大学受験などで化学を使った人からすると、なんてことない試験だと思います。高校以降で化学をあまり勉強していない人には、かなり難関の試験になると思います。

管理人は高校では理系選択だったので、高校化学は勉強しました。しかし、当時は勉強のやる気がなく中途半端にしか勉強してなかったので、今回の危険物甲種では苦戦しました。
【受験動機】
実は、今回の受験以前にも危険物甲種の受験を考えていました。その時の理由は、技術士という資格試験で科目免除ができるからというものでした。結局、仕事と実生活が忙しくなり、勉強が続きませんでした。現在は、技術士の科目免除制度はなくなってしまいました。
今回の受験では会社の資格手当を増やそうと思い、甲種を受験しました。しかし、よく考えた結果、会社には資格を提出しませんでした。
【参考書】
(1) 甲種危険物取扱者試験
危険物乙4で有名な資格出版の参考書です。消防試験研究センターは、消防設備士試験と危険物取扱者試験を実施しています。両試験とも年に何度も開催され、本試験では問題冊子を持ち帰ることができません。なので、市販の過去問題集というのは基本的に存在しないはずです。
危険物取扱者試験は年に何度も開催される試験です。実際の試験では、同じ問題を使いまわしている可能性が高いです。つまり、過去問演習ができれば合格できる可能性は高まります。
この問題集は危険物乙4版が以前から発売されており、過去問を収録しているとうたっていました。実際に乙4の本試験でも同じ問題を見たという方もいるようです。甲種の問題集もうたい文句通り、過去問が収録されている可能性が高いです。
私の知り合いの方の話ですが、毎年会社の誰かが消防試験研究センターの試験を受験するそうです。その時にAさんには、出題問題の1番目と2番目を記憶してこい!と指示し、Bさんには、出題問題の最後を記憶してこい!と指示したりするそうです。
この問題集がどのような形で作られたかは分かりません。市販の過去問が存在しないはずの資格試験で過去問らしき問題集があるのはよくある話です。
これから参考書を購入して受験する方は、この問題集を購入してみたらいかがでしょうか?
(2) わかりやすい! 甲種危険物取扱者試験
参考書兼問題集です。理系(化学系)の人や基礎能力が高い人であれば、これ一冊で簡単に合格できると思います。著者の工藤政孝氏は消防設備士の参考書でも有名です。
甲種の場合、法令と性質・消火はこれ1冊をしっかり勉強すれば問題ないと思います。
問題は物理・化学で、受験者の基礎能力に大きく左右されます。無勉強でも物理・化学で満点が取れる人もいれば、高校化学の基礎から勉強が必要な人もいると思います。物理・化学に関しては、どの参考書をやれば安心とかはないと思います。
(3) 本試験形式! 甲種危険物取扱者 模擬テスト
模擬テスト形式で、本試験形式の模擬テスト×5セットです。1セット分は、法令15問+物理・化学10問+性質・消火20問の全45問です。45問x5セットで225問掲載されています。巻末に物理・化学対策として5問あり、これ1冊で230問の問題演習が可能です。
参考書部分はほとんどありません。解説は詳しいので、勉強はしやすいです。
物理・化学に自信がない方は、問題数をこなした方が良いというのが個人的な意見です。基本的な化学の知識がないから、問題パターンを覚えてしまおうという方法です。
私も3冊購入して徹底的に問題演習しました。複数の参考書を購入して勉強するならば、管理人的にはここに紹介している順番がおすすめです。
(4) 甲種危険物予想問題集
こちらも本試験形式の問題集です。全8セットありますので、45問x8セットで360問の問題演習ができます。何度か改訂されていますが、管理人は中古で500円程度で購入しました。
解説の質も悪くないし、問題数も多いので安く購入できれば悪くないと思います。ただ、正規の値段で購入するならまず上の3冊をおすすめします。
【勉強方法】
法令
法令は完全に暗記です。わかりやすい! 甲種危険物取扱者試験には、語呂合わせがのっています。同じ著者である工藤氏の消防設備士試験の語呂合わせは傑作レベルです。危険物の参考書の語呂合わせはイマイチですが、保安距離の語呂合わせなどは覚えやすかったです。
参考書で太字になっているところは確実に覚えるべきです。乙種の法令より細かいところを聞かれます。乙種の法令は、参考書の問題をやり込むだけで軽く合格点に届きました。甲種も同じように問題をやり込みましたが、合格点ギリギリでした。
法令は参考書を1冊しっかり読み込む必要がありそうです。
物理・化学
物理・化学は受験者により差があります。学生時代にしっかりと化学を勉強した人には楽勝な科目だと思います。それ以外の人にはかなりの難関になると思います。
モル計算は必須です。化学反応式を書かせて、そこからモル計算をさせるというレベルの問題は当たり前のように出題されます。有機化学では、アルカン、アルケン、アルキン等の区別がつくのは当然として、基本的なものは分子式や名称も覚えておく必要があります。
簡単な人には簡単です。しかし、なかには高校化学の基礎から勉強が必要な人もいると思います。そんなことを言っていたら、弘文社さんがそれっぽい参考書を出版してきました(笑)。
わざわざ物理・化学を勉強し直さなくても、過去問などでパターンを覚えて力押しで攻めても合格できると思います。ただし、複数回受験する覚悟は必要です。
性質・消火
性質・消火も法令と同じで暗記です。わかりやすい! 甲種危険物取扱者試験の各類の章末の第○類危険物のまとめが役に立ちました。
反応で発生するガスなどは、一度化学式で覚えると記憶に定着しやすいかもしれません。それ以外は、あまり使える語呂合わせもないので、ひたすら暗記するしかないと思います。
性質・消火は範囲が広いだけで難易度は乙種とあまり変わらないと感じました。問題演習しながら暗記するだけで十分だと思います。

【試験本番】

試験本番で特に印象的だったのが、モル計算の問題です。物質の燃焼により発生する二酸化炭素や水の量を誘導的に求めさせて、そこから物質名を答えさせる問題でした。答えはエチレンだったのですが、勉強不足でエチレンの化学式を忘れていましたw
管理人はこの程度のレベルです。これでも何とか合格できました。
【合格後】
仕事では使いません。資格手当てもいただいていません。勉強した知識を活かす機会もほぼないと思います。何のために受験したんだ!と言われそうですが、返す言葉がありません(笑)。
設備管理やビルメンでもこの資格を使う機会はあまりないと思います。危険物乙4だけで十分だと思います。多くの薬品を扱ったりする工場などでは重宝されるのかもしれません。
資格としての危険物甲種
私が働く設備管理(ビルメン)業界では、使わない資格にも手当が出る場合が多いです。危険物取扱者に関しては、現場にはボイラーや発電機がある場合があります。燃料は主に重油の場合が多いです。つまりほとんどの現場は危険物乙4だけで十分なのです。
設備管理業界は人材を現場に送り込む仕事です。客先の現場に提出する経歴書には一つでも多くの資格を書きたいというのが本音でしょう。本来は危険物乙4だけで十分なのですが、その上位資格である危険物甲種を取得しておくと見栄えが良いといったところでしょうか?
逆に4類以外の危険物を使う研究所や工場では、危険物甲種が役に立ちます。しかしそういった仕事の方が危険物甲種の資格手当てがつかない場合が多いです。資格手当て自体がないことも多かったりします。その代わり工場や研究所は給料が高い場合が多いです。
【最後に】
危険物取扱者の勉強はこれで終了です。また何かあったら少し記事を書きますが、免状を埋めるために乙種2類、6類、丙種などを受験することはありません。私は資格マニアですが、免状を集める事が目的ではありませんので。