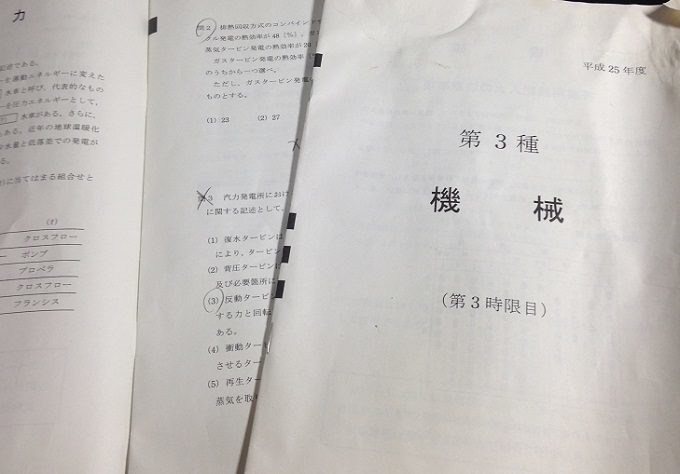危険物甲種は、乙種に比べて難しいと言われます。
甲種の性質・消火は乙種1類~6類までの全範囲が問われますが、範囲が広いだけで乙種とそれ程変わりません。法令に関しても、暗記する内容はほぼ同じです。
乙種と甲種の難易度の違いは、物理・化学の難易度の差が大きいです。
物理の難易度の差
甲種は計算問題が難しい
乙種の物理では、単に公式に数字を入れれば問題が解けました。甲種では、公式を理解しないと解けない問題も多いです。
例えば、乙種ではボイル・シャルルの公式を丸暗記するだけで問題が解けました。甲種だと気体の状態方程式、PV=nRTを理解する必要があります。状態方程式のn(mol)が、質量/分子量ということを理解できないと解けない問題もあります。
乙種はモル計算を捨てても合格できますが、甲種ではモル計算が必須です。モル計算は、高校化学の初学者にとって最初の壁でもあります。
管理人は超進学校に通っていましたが、高校1年で習うこのモル計算ができない人がたくさんいました。
甲種の物理は高校1年生レベル
乙種の熱計算では、「比熱A[J/(g・K)]の液体Y[g]の温度を、20℃から40℃に上昇させるのに必要な熱量を求めよ。」というような問題がメインです。数値を公式にあてはめて、掛け算していくだけで答えが出ます。
この場合、(40℃‐20℃)×Y[g]×A[J/(g・K)]で求められます。
簡単ですね。
甲 種では、物質が二つでてくる場合があります。「比熱A[J/(g・K)]で80℃の物質X[g]を30℃の水1kgの中に入れると全体の温度は何度になる か。」という問題もあります。この問題を解くには、水の比熱を暗記しておき、自分で連立方程式をたてる必要があります。
どれも乙種より少し難しいだけですが、公式の丸暗記では対応できない問題です。知識的には高校1年生レベルですが、甲種では公式を理解して使いこなす必要があります。
化学の難易度の差
化学式の暗記は必須
乙種では、化学式は意識しなくても問題が解けました。甲種では、化学式を意識するだけでなく暗記している必要があります。
水(![]() )くらいは誰でも分かると思いますが、甲種ではメタノール(
)くらいは誰でも分かると思いますが、甲種ではメタノール(![]() )などの少し複雑な物質の化学式も暗記しておく必要があります。
)などの少し複雑な物質の化学式も暗記しておく必要があります。
化学の基本法則は知ってて当然
質量保存の法則、倍数比例の法則、定比例の法則、アボガドロの法則。高校化学をしっかり勉強したことがある人は、これらの法則を自然と使いこなせているはずです。甲種では、これらを知っていることを前提として、化学反応式の計算問題が出題されます。
高校数学の知識も出題される
乙種では酸と塩基の分野は、基本的なことだけ暗記してれば大丈夫でした。甲種では、pH(水素イオン指数)を計算させる問題もあります。
この手の問題を解くには、電離の知識とlogという高校2年生レベルの数学知識が必要です。化学や物理だけでなく、数学の知識も要求されます。
理系の人だと知ってて当然ですが、それ以外の人にはとっつきにくいのかもしれません。
無機化学だけでなく有機化学も
甲種だと有機化学も出題されます。有機化学は、現役の高校生でも苦手な人が多い分野です。
世の中であなたが手にするほとんどの物質が有機化学で表す有機物です。
とにかく難しい用語が多いです。ヒドロキシル基などの官能基、飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸の違いなど有機化学をかじった事のない人には理解しにくいと思います。
危険物甲種必要勉強時間目安
危険物甲種の必要勉強時間
化学初学者
30時間~300時間
中学化学レベル
20時間~200時間
高校化学レベル
20時間~50時間
大学化学レベル
10時間~50時間
危険物乙種合格者
0時間~200時間
結論
危険物乙種の物理化学は中学生+αレベルだと思います。危険物甲種は高校生レベルです。高校以降で化学をしっかり勉強した人には、さほど難しくないと思います。それ以外の人には、非常に難しく感じると思います。
この物理化学の難易度の差が、乙種と甲種の難易度の差だと思います。
法令や性質・消火も乙種と甲種で難易度は違いますが、物理・化学ほどの差はありません。

危険物取扱者試験は、完全に理解できなくても問題演習しながら暗記してしまえば、合格できる可能性が十分にあると思います。試験の出題パターンは、試験開催日ごとに変わります。危険物甲種を複数回受験する覚悟でのぞめば、暗記勉強だけでも合格可能だと思います。
幸いなことに、危険物乙4の過去問が掲載されていることで有名な公論出版さんの参考書の危険物甲種版が発売されました。この問題集で過去問の演習をして、出題パターンを暗記すれば、合格の可能性が高まると思います。
危険物甲種のまとめは以下の記事になります。