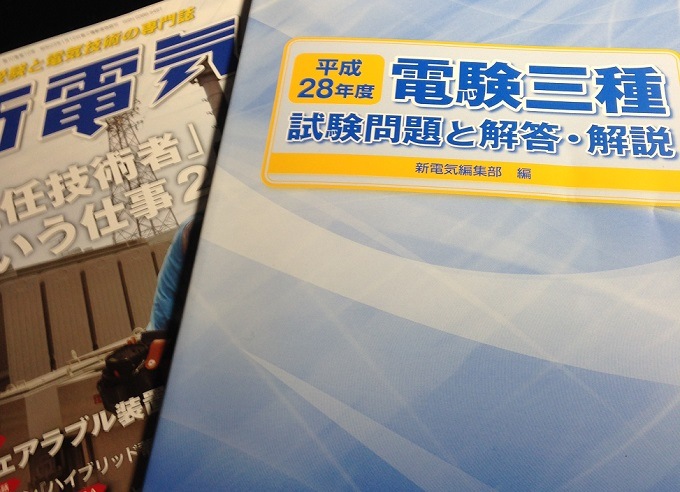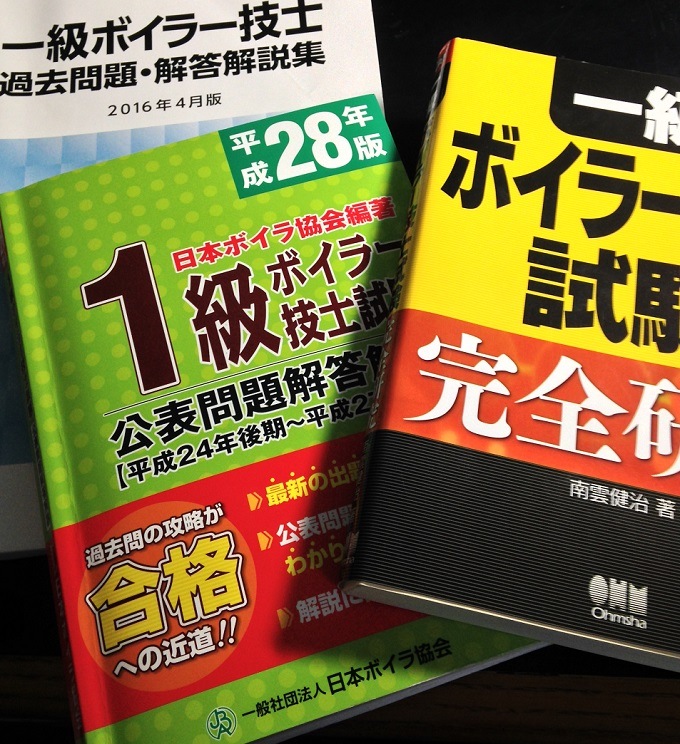消防設備士乙種7類は、科目免除を使うと少ない勉強量で合格できる資格です。
第2種電気工事士に合格した人が、履歴書の資格欄を埋めるために取得したりします(笑)。この記事では、乙種第7類消防設備士の難易度、参考書、勉強法、管理人の体験談などを紹介していきます。
【受験概要】

【資格名称】乙種第7類消防設備士
【受験年度】平成28年度
【試験点数】
<筆記試験>:筆記全体(93%) ≪法令(90%) 機能・構造(100%)≫
<実技試験>:免除
消防設備士7類は、漏電火災警報器についてです。非常にイメージしにくいかもしれません。実を言うと、管理人も見たことがありません。
ラスモルタル造の建築物のみに設置義務があります。大きな建物や新しい建物には、設置されていないようです。資格自体の需要も高くないです。
漏電火災警報器の仕組みを理解するには、ある程度電気の知識が必要です。合格するのは簡単ですが、理解して合格している人は多くないと思います。
消防設備士乙7の科目免除
| 主な科目免除表 | 電気工事士 | 電気主任技術者 | 消防設備士 | |
| 基礎的知識 | 電気 | ○ | ○ | |
| 消防関係法令 | 共通 | ○ | ||
| 7類 | ||||
| 構造・機能・ 工事・整備 | 電気 | ○ | ○ | |
| 規格 | ||||
| 実技試験 | 鑑別 | ○ | ||
乙7の受験でどの科目免除を使うかは、意見が分かれるところだと思います。
合格するだけなら、電気工事士の免除は絶対に利用したほうが良いです。鑑別がまるまる免除になるのはおいしすぎます。「自分はどうしても漏電火災警報器の勉強がしたい!」という殊勝な方は、免除なしでチャレンジしてみてください。
ちなみに管理人が受験した会場では、免除を利用していない受験者が多かったです。実際に免除を使わない人も多いようです。
ちなみに、電気工事士の免除なしでの合格率は50%台。電気工事士の免除ありでの合格率は70%台です(消防試験研究センター宮城支部さんありがとうございます)。
消防設備士免除に関しては、使っても使わなくてもいいと思います。消防設備士免除を使っても、試験の合格率はたいして変わらないそうです。最近他の類の消防設備士に合格したばかりという方は、別に消防設備士免除を使わなくても良いかもしれません。
消防設備士免除を使うと、消防法令関係が全4問になります。消防設備士では、科目ごとの合格ラインは40%以上で、全体で60%以上です。つまり、この4問中2問正解(50%)しないと、その時点で科目合格ラインに届かず不合格確定です。
意外と危ない橋です。消防設備士免除を使えば勉強量は減らせますが、本番でミスができません。逆に免除を使わなければ全10問ですので、少し余裕ができます。
この消防設備士免除を使うかどうかは、受験者の戦略次第です。
【難易度】
乙種7類(電工免除なし):★★★☆☆☆☆☆☆☆ (3/10 やや易)
乙種7類(電工免除あり):★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10 易しい)
過去の合格率 (平成28年7月まで)
| 受験年度 | 合格率 |
| 平成23年 | 61.4% |
| 平成24年 | 60.2% |
| 平成25年 | 61.3% |
| 平成26年 | 59.7% |
| 平成27年 | 59.0% |
| 平成28年 | 57.4% |
| 平成29年 | 59.1% |
| 平成30年 | 58.7% |
| 令和元年 | 56.9% |
| 令和2年 | 59.0% |
難易度的には、電気工事士免除を使うかどうかで大きく変わります。免除を使わなければ、消防設備士の乙種4類や6類に近い難易度だと思います。
電気工事士免除を使うと、国家試験としてはかなり簡単な部類です。
合格率は6割前後で安定しています。でも、管理人が受験した試験会場では、免除を使わずに受験していた人もかなりいました。
勉強時間
勉強期間は63日間、勉強時間は14時間33分。
第2種電気工事士の科目免除だけ使いました。
消防設備士乙7は、実技試験を免除すると非常に簡単な試験です。第2種電気工事士の免除を使うと、実技試験がすべて免除になるので勉強時間が半減します。更に他の類の消防設備士をお持ちの方は、消防設備士の免除も使うと10時間くらいの勉強で合格できるかもしれません。
受験時の主な所持資格:消防設備士甲種4類、電験3種
勉強時間の目安
資格勉強になれていない人で30時間~50時間くらい。資格試験になれている人で、20時間~30時間くらいでしょうか。
電気工事士の免除を使うと、10時間~30時間。電気工事士と消防設備士の免除を使うと、5時間~20時間くらいでしょうか。
電気工事士の免除を使うかどうかで難易度も勉強時間も大きく変わります。
【受験動機】
消防設備士をコンプリートするための受験です。仕事で使うこともありませんし、会社から資格手当なども出ません。純粋に資格マニアとしての受験です。
消防設備士の免状所持者は、資格を取得すると5年に1度講習を受講する必要があります(最初の講習は、資格取得後最初の4月1日から2年以内)。講習は全部で4つあります。
| 免状の種類 | 講習の種類 |
| 甲種特類 | 特殊消防用設備等 |
| 1・2・3類 | 消火設備 |
| 4・7類 | 警報設備 |
| 5・6類 | 避難設備・消火器 |
私はすでに甲種4類、甲種5類、乙種6類を所持しているので、警報設備と避難設備・消火器の二つの講習は受講する必要があります。この場合、1類~3類のいずれかの免状を取得してしまうと、あらたに消火設備講習も受講しなくてはなりません。
なるべく講習を受講したくないので、1類~3類は平成29年4月まで受験しません。
この記事を書いているのが平成28年10月。平成29年の3月までに1類~3類のどれかに合格してしまうと、平成29年4月1日~平成31年4月1日に1・2・3類の消火設備講習を受講しなくてはなりません。
平成29年4月以降に1類~3類のどれかに合格した場合、平成30年4月1日~平成32年4月1日に1・2・3類の消火設備講習を受講すればOKになります。1年の差ですけど、結構でかいです。
【参考書】

(1) わかりやすい!第7類消防設備士試験
消防設備士や危険物の参考書は、弘文社が強いですね。非常によくまとまっています。私が受験した回の試験問題は、すべてこの参考書にほぼ同じ文面でのっていました。
この参考書の形式は、参考書+問題集です。問題数はあまり多くないので、参考書をある程度読みこむ必要があります。そういった勉強が苦手な方は、下の問題集タイプのものがおすすめです。ただ、内容の詳しさではこちらが一枚上です。
(2) 本試験によく出る!第7類消防設備士問題集
上の参考書の問題集タイプです。参考書の部分がほとんどありません。問題を繰り返し解いて頭にインプットするといった勉強法に合っています。試験内容のカバー率では、上の「わかりやすい~」に劣りますが、合格点を取るだけならこれ1冊で十分だと思います。
ちなみにこちらの問題集の方が、上の参考書タイプより売れているようです。
【勉強方法】
筆記試験
意外と細かい知識を問われました。法令は簡単な問題が多かったですが、機能・構造で細かい数字系の知識を多く問われました。
実際に出題された問題は、以下の記事にのせています。

実技試験
管理人は実技試験を受験していないので分かりません。ただ、漏電や地絡について理解していないと、解けない問題が多いです。電気の初心者にとっては結構なハードルだと思います。
【試験本番】
試験本番の記事は、以下になります。

【合格後】
仕事では使いません。漏電火災警報器を見たこともありません。単なる資格マニアの自己満足です。会社によっては、500円~1000円くらい手当てがつく場合もあるかもしれません。
当社では、「またお前資格取ったのか…」と言われておしまいです。
【最後に】
消防設備士7類の受験を考えている方は、7類の前に1類、4類、6類を優先させた方が良いと思います。「どうしても履歴書の資格欄を埋めたいんだ!」って人は止めません。転職活動に使う場合、資格に詳しい面接官には、効果がない可能性が高いです。
ただ単に資格をたくさん持っていても意味がなかったりします。