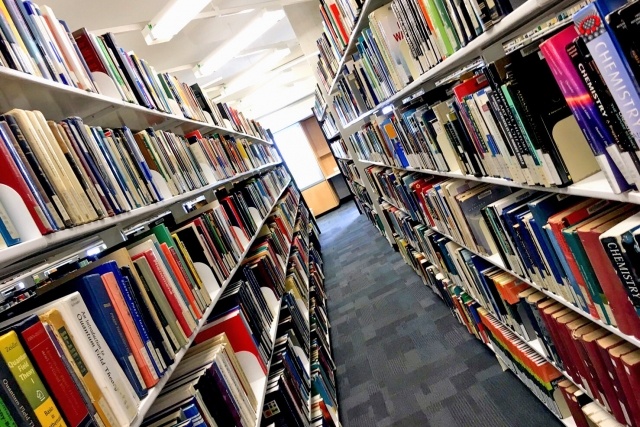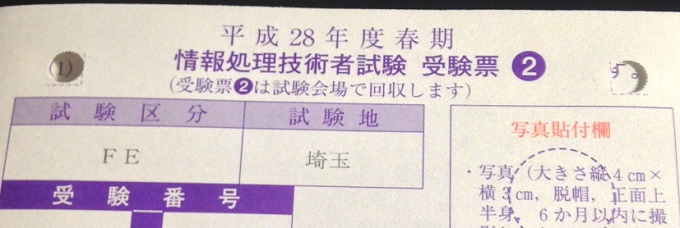消防設備士5類は、消防設備士試験のなかでも勉強しにくい分野です。避難設備は身近にある設備でイメージしやすいのですが、マイナーな資格のため勉強法が限られます。この記事では、消防設備士5類の難易度、参考書、勉強法、管理人の体験談などを紹介していきます。
【受験概要】

【資格名称】甲種第5類消防設備士
【受験年度】平成28年度
【試験点数】
筆記試験:筆記全体(80%) ≪法令(93%) 基礎知識(80%) 機能・構造(70%)≫
実技試験:実技全体(77%)
消防設備士5類は、避難設備の分野になります。避難はしごや避難階段などが分かりやすいかもしれません。救助袋や緩降機などといった設備もあります。

合格点
筆記試験全体で60%以上、実技試験全体で60%以上の正解で合格です。
筆記試験は、法令(15問)、基礎知識(10問)、機能・構造(20問)の3科目あります。それぞれの科目の最低合格点は40%で、どれか1科目でも40%未満になると、筆記全体で6割取れていても不合格です。
実技試験は科目の区別はなく、全部で7問です。実技試験は部分点が多いので、完答できなくても点数がもらえる場合があります。全7問の6割以上で、5問完全正解しなくてはならないというわけではありません。
消防設備士甲5の受験資格
消防設備士は甲種からは、受験資格が必要です。受験資格の詳細はこちらになります。今回の甲5類の受験では、電気工事士の免状で受験申請しました。
今回甲5類に合格したことで、次回から甲種の受験資格の証明が簡単になります。最初に消防設備士甲種を受験する時は、書類を郵送する必要があります。一度なんらかの消防設備士甲種を取得すると、次からはネットで受験申請が可能となります。

消防設備士5類の科目免除
消防設備士は、科目免除制度があります。詳細はこちらになります。他の類の消防設備士や技術士を持っている人が、主に科目免除の対象となります。
【難易度】
甲種5類:★★★★☆☆☆☆☆☆ (4/10 普通下位)
乙種5類:★★★☆☆☆☆☆☆☆ (3/10 やや易)
過去の合格率 (平成27年度は平成28年1月まで)
| 受験年度 | 甲5合格率 | 乙5合格率 |
| 平成23年 | 29.3% | 42.5% |
| 平成24年 | 26.3% | 36.8% |
| 平成25年 | 33.3% | 40.9% |
| 平成26年 | 32.8% | 43.1% |
| 平成27年 | 32.1% | 39.2% |
| 平成28年 | 36.7% | 46.6% |
| 平成29年 | 37.8% | 42.5% |
| 平成30年 | 35.2% | 39.1% |
| 令和元年 | 32.3% | 35.8% |
| 令和2年 | 36.8% | 41.2% |
難易度的には、危険物甲種と同じ★5個程度かなと思いました。ただ、5類は出題範囲が比較的狭いので★4としました。
合格率は甲種5類が3割前後、乙種5類が4割前後で安定しています。甲種5類に関しては、市販の参考書だけではカバーしきれない知識が出題されます。年々ネット上にそういった試験の出題情報が蓄積されているのも合格率上昇の要因だと思います。
本当かどうか分かりませんが、消防設備士試験の講習会などでも、「ネットで試験情報を探してみてください」と講師の方が言ったそうです。
参考書にのっていない知識も、建築屋さんや防災屋さんにとっては常識なのかもしれません。電気が比較的得意で機械分野が苦手な管理人にとって、5類は相性の悪い試験でした。
勉強時間
勉強期間は101日間、勉強時間は43時間17分。
消防設備士は乙種6類以来で数年ぶりの受験でした。法令はほとんど忘れていました。5類は勉強範囲は狭いのですが、参考書にのっていない知識も問われます。参考書の勉強だけならすぐに終わりますが、最後にネットで情報を集めたりして意外と時間がかかりました。
受験時の主な所持資格:消防設備士乙4、乙6、危険物甲種
勉強時間の目安
勉強時間の目安は、資格試験に慣れていない人で100時間~200時間くらい。他の類の消防設備士を取得済みの方などは、50時間~100時間くらいでしょうか。
効率よく勉強すれば、20時間~30時間程度でも合格可能でしょう。
【受験動機】
消防設備士をコンプリートするための受験です。仕事で使うこともありませんし、会社から資格手当なども出ません。純粋に資格マニアとしての受験です。
消防設備士の免状所持者は、資格を取得すると5年に1度講習を受講する必要があります(最初の講習は、資格取得後最初の4月1日から2年以内)。講習は全部で4つあります。
| 免状の種類 | 講習の種類 |
| 甲種特類 | 特殊消防用設備等 |
| 1・2・3類 | 消火設備 |
| 4・7類 | 警報設備 |
| 5・6類 | 避難設備・消火器 |
私はすでに乙種4類と乙種6類を所持しているので、警報設備と避難設備・消火器の二つの講習は受講する必要があります。この場合、1類~3類のいずれかの免状を取得してしまうと、あらたに消火設備講習も受講しなくてはなりません。
なるべく講習を受講したくないので、甲種4類、乙種7類、甲種5類を最初に取得しようと考えました。4類と7類は比較的得意な電気分野が多いので、まずは苦手な機械分野が多い甲種5類を受験しようと考えました。
【参考書】

(1) よくわかる!第5類消防設備士試験
消防設備士や危険物の参考書は、弘文社が強いですね。市販の参考書のなかでは、かなり試験内容に近いと思います。シャックルやシンブルといった頻出事項や避難設備の操作手順を詳しくのせているのはこの参考書だけです。※オーム社の新しい参考書にものっています。
5類の勉強では、最後はネットをさまよいながら勉強することになります。しかし、最低1冊は参考書を購入する必要があります。この参考書が一番おすすめです。
(2) ラクラクわかる! 5類消防設備士 集中ゼミ
私が5類を受験した後に発売された参考書です。この参考書もおすすめです。過去に出題された問題を分析して、頻出事項や細かい知識までカバーしている参考書です。内容が詳しすぎるところがあり、少し難易度が高い参考書です。
5類の参考書は、よくわかる! 第5類消防設備士試験 か ラクラクわかる! 5類消防設備士 集中ゼミのどちらかがおすすめです。オーム社のこのシリーズは、まともな参考書が多いですね。
(3) ラクラク解ける!5類消防設備士 合格問題集
上の「ラクラクわかる!~」の問題集版です。オーム社のこのシリーズの問題集や参考書は、以前のものと比べて出題範囲のカバー率が上がっています。おすすめのシリーズです。
(4) 図解でマスター 5類消防設備士
イマイチです。この参考書の降下空間や操作面積などをまとめた表は使えました。それだけのために購入する必要はないと思います。
(5) 消防設備士 受験直前対策
日本消防設備安全センターが出版している参考書です。試験センターとの関係性は分かりませんが、公式の参考書といった位置づけでしょうか?問題数も少ないですし、参考書としてもそこまで詳しくないです。1000円ちょっとで買えるのが強みかもしれません。
購入したい方は、こちらから購入できます。
(6) 5類消防設備士 精選問題集
精選問題集という響きを聞くと、同じオーム社が出版している危険物乙4の名参考書、乙4類危険物試験精選問題集 を思い出します。期待して購入しましたが、イマイチでした。悪くはないのですが、まだ実用レベルではありません。
(7) 5類消防設備士 筆記×実技の突破研究
5類の参考書は、ほとんどがオーム社のものです。筆記×実技の突破研究はそのなかでも一番出来が悪いと思います。法令などは試験の難化に対応できるように、難しい問題をのせているのかもしれません。それが本試験の傾向と合っていないと感じました。
【勉強方法】
筆記試験
今回受験した感想としては、筆記試験も難化傾向なのかなと感じました。以前の消防設備士試験は、筆記試験は簡単で問題は実技試験でした。最近の消防設備士試験は、筆記試験もしっかりと対策する必要があると思います。
法令
法令の勉強は、他の類の消防設備士の参考書が役に立ちます。他の類の参考書をお持ちの方は、消防関係法令の共通部分は他の類の参考書でも勉強した方が良いです。
消防設備士の他の類を持っていて免除できるからといって、消防関係法令の共通部分を免除してはいけません。筆記試験も難しくなっています。比較的簡単な共通部分を削って全体で6割を目指すのはおすすめしません。
基礎知識
今回の受験では、基礎知識の分野でネズミ鋳鉄の特徴が出題されました。他にも溶接のアンダーカットやオーバーラップ、焼き入れ・焼き戻し・焼なまし・焼ならしなどは覚えておく必要があります。比例限度、降伏点、弾性限度なども頻出分野です。
基礎知識は計算部分が比較的簡単です。計算で得点を稼げるようにしておくと楽になると思います。許容応力、安全率、引張り強さやモーメントの計算はできるようにしておきましょう。滑車の問題で、動滑車が一つ増えると重量の半分が軽減されるという問題も頻出です。
機能・構造
機能・構造では、降下空間や操作面積などの細かい数値が問われる可能性が高いです。参考書で太字になっている数字は覚えておいた方が良いです。あとは、緩降機や救助袋の操作方法も暗記必須です。よくわかる!第5類消防設備士試験には図つきで掲載されています。
試験回によっては、「JIS G○○○○」の形で避難設備の材質を問う問題が出題されたそうです。私が受験した回では出題されませんでした。材質の問題は、完全に捨てていたので助かりました。
実技試験
実技試験は、よくわかる!第5類消防設備士試験の勉強と併用して、某巨大掲示板の過去ログでの勉強がおすすめです。「消防設備士5類 2ch」とでも検索して、過去ログをすべて読みましょう。非常に役に立つ情報が多いです。
シャックル、シンブルなどの頻出の鑑別問題から避難設備の操作方法などもよく出題されているようです。甲5類の製図問題は4類などと比べると簡単です。それでも本試験の問題は、参考書の問題よりレベルが高いです。
モーメントなどの計算問題は理解していれば、比較的簡単です。今回の受験では、計算問題と合わせてアンカーの埋め込み深さや穿孔深さなども出題されました。アンカーの呼び径と合わせて覚えておく必要がありそうです。
【試験本番】

【合格後】
仕事では使わないので、資格マニアとしての受験です。甲5類→甲4類→乙7類と勉強していく予定です。
消防設備士4類なら多少役に立つのですが、5類はあまり使う機会がありません。大きなビルに勤めている方なら、避難設備を目にする機会も多いのかもしれません。
【最後に】
消防設備士は、講習の受講義務があるので継続的にお金のかかる資格です。コンプリートすると5年間で7000×4講習で3万円近くかかります。私のように会社から資格手当てがもらえない人は、計画的に受験した方が良いと思います。