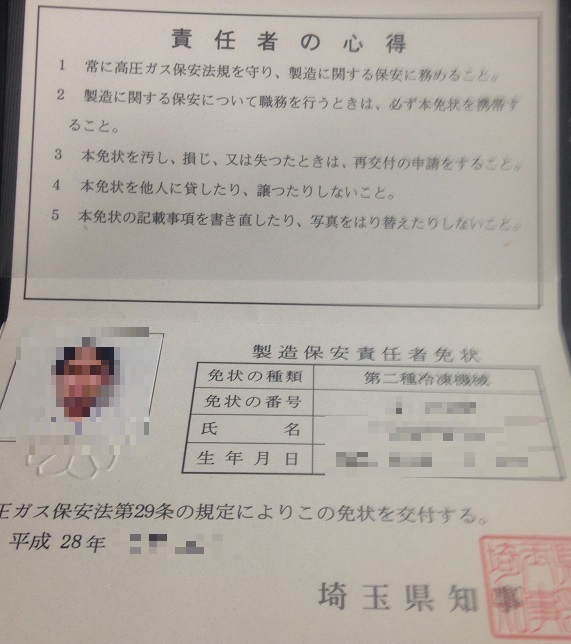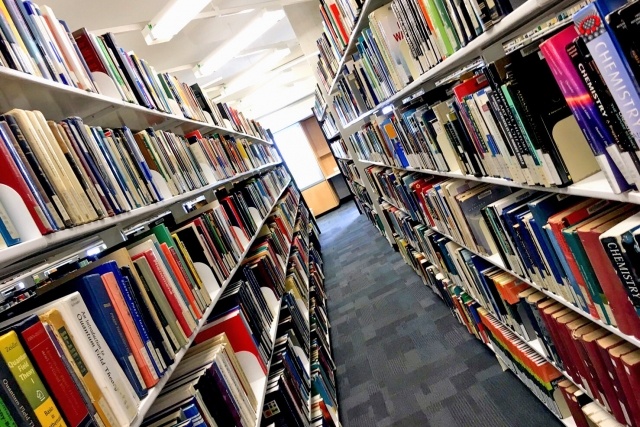第142回日商簿記検定3級試験になぜか合格してしまいました。受験後には自己採点するのも嫌になるほど不合格の予感がしましたが、結果は合格でした。結局、簿記3級などの下位資格は、何も分かっていなくても合格できる試験なんだなと強く感じました。

簿記3級になんとか合格はしたが…
簿記3級に合格しましたが、何も理解していない感覚があります。
簡単な仕訳ができるくらいで、簿記のことなどまったく理解していません。いまだに貸方と借方の区別があまりついていなかったりします(笑)。
40時間未満の勉強では、この程度なのかもしれません。
試験本番でも、当然のごとく貸方と借方の数字が合いませんでした。その時点で不合格を覚悟したのですが、部分点がもらえる簿記の採点制度に助けられた模様です。
いつ郵送されてくるのか分かりませんが、試験点数を見るのが楽しみです。

第142回の簿記3級の合格率は意外と低かった
第142回の簿記3級の合格率は30%を下回っているようです。私が受験した自治体でも27~28%程度でした。
合格率が50%以上の回もあったことを考えると、簿記3級も難化傾向なのかもしれません。
と言うか、いろいろな分野の資格試験を見回しても、簡単になった資格試験を探す方が難しいかもしれません。資格試験も簡単に合格させては儲か(ry…独り言です。
簿記の試験会場は華やかだった
簿記3級の試験会場には30過ぎのおっさんなどほとんどいませんでした。若い女性や若い男性が多く、雰囲気が華やかでした。
くたびれたおっさん(注:管理人も含む)しかいない某資格試験の会場とはまったくイメージが違いました。
簿記2級も受験予定ですが、会場にキモいおっさんがいてもそっとしておいてください。管理人からの切なるお願いです。
下位資格に合格してもなにも分からない件
簿記3級に合格しただけでは、何も分かってない感が強かったです。転職市場でも簿記は2級からと言われていることに少し納得できました。
資格としては、簿記1級からしか評価されないと言っている方もいるみたいです。
これは、私がここ数年勉強してきた電気の分野でも同じです。
電気工事士という暗記だけで合格できる下位資格
電気の分野は非常に奥が深いと感じています。電気の資格で簿記3級と同じ立ち位置なのが、第2種電気工事士です。実技もある試験なのですが、筆記試験の電気計算の部分をまったく理解していなくても解けてしまうという試験なのです。
私は以前、職業訓練校で中学の数学も怪しい高卒の子たちと一緒に第2種電気工事士の勉強をしましたが、そのほとんどが、電気計算の基礎さえも理解できていませんでした。
しかし、結果は全員合格でした。
上位資格の第1種電気工事士も同じです。こちらも暗記で合格できてしまいます。電工1種はしっかり勉強すれば、上位試験の足がかりになる試験です。
しかし、周りを見ると小手先の暗記で対応している人が多かったです。
暗記で電気工事士の筆記試験に合格した人が、上位資格の電験3種(第3種電気主任技術者)に挑戦すると最初の一歩でつまずきます。電験3種は考えさせる試験なので、しっかり計算の意味を理解していないと解けないのです。
電験3種も下位資格
そして電験3種の上の電験2種(第2種電気主任技術者)になると、2次試験というとてつもなく難しい試験が追加されます。この2次試験に合格するのに5年も10年もかかる人が多い印象です。
管理人は、最初から電験2種に挑戦することを諦めました。
これほど難しい試験なのに、なぜか電験のネット上の評価が低いのです。特に2種レベルに合格するには、相当の努力や才能が必要になります。
電験や技術系資格の評価を上げるために、このブログが一役買えないかと思っています。それが第一線で働かれている技術者さん達の地位向上にもつながるのかなと思っています。底辺労働者の私にできるかは分かりませんが、そういう思いで記事を書いています。
最後に
簿記3級に合格したので、とりあえず簿記2級の勉強を始めようと思います。簿記の適性はなさそうですが、行ける所まで行ってみようと思います。
簿記3級で苦労したので、簿記2級は100時間以上は勉強しようと思っています。