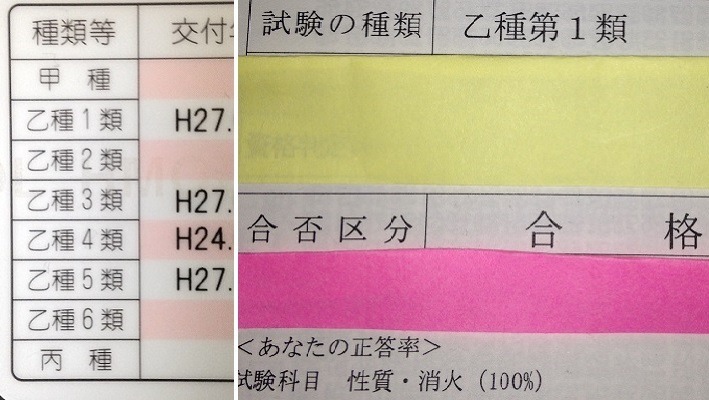電験3種の最難関科目といわれるのが機械です。その機械の勉強法のひとつに、工業高校の教科書を使った学習という選択肢があります。教科書は非常に内容が詳しく、図が多く分かりやすいです。その学習法について紹介したいと思います。
最難関科目機械
電験3種の中でみんなが大好きな科目「機械」。私も好きすぎて(理解できなくて)、300時間以上勉強しました。それでも理解できませんでした。
機械の合格率と難易度
電験3種の合格点は、難しいほど低くなります。最近は60点が合格点の年が多いですが、難易度はあまり変わってないようです。
2020年の機械科目の合格率はなんと6.7%!!!
簡単な年は20%(令和元年)に乗りますが、それ以外はだいたいが10%代で安定しています。
機械の次に難しいと言われる科目は理論です。しかし、理論はここ10年以上、常に10%以上の合格率があります。
機械は難しい年と簡単な年の差が激しい印象です。
管理人は、機械オンチなので機械が一番苦手です。
機械が難しい理由は2つあります。
1つ目は、機械の範囲の広さ。「これだけ機械」という参考書がありますが、同シリーズの「これだけ理論」の約1.5倍の厚さがあります。それだけ勉強する範囲が広いのです。
2つ目は、機械の文章問題が難しいという事です。理論は計算問題が約8割なので、計算が得意な人にはそこまで難しい科目ではありません。
対して、機械は半分近くが文章問題です。なので、計算力と理解力の両方を要求されます。
効率的に機械に合格するために
範囲が広い機械ですが、出題の5割程度は「電気機器」という分野からです。電気機器は、直流機・変圧器・誘導機・同期機・パワーエレクトロニクスなどの分野で構成されます。
電験3種の合格点は高くても60点。電気機器の問題にすべて正解すれば、他が不正解でも合格できる可能性さえあります。全問正解というのはさすがに難しいかもしれませんが、電気機器を集中的に勉強すれば、合格する確率は上げられます。
照明や電気化学などの分野は、ラッキー問題が出題される時があります。それを考えると、電気機器だけ勉強するというのはおすすめしません。
1冊参考書を仕上げて、その後電気機器の勉強に時間を使う勉強法が良いかもしれません。
私は電気機器を集中的に勉強しましたが、極度の機械音痴なので機械のイメージができませんでした。誘導機の絵や図を見てもいまいちピンと来ませんでした。仕方ないので電気機器以外も徹底的に勉強しました。
結局、300時間以上機械を勉強しました。
電気機器が苦手ではない方は、電気機器の勉強に使う時間を増やすといいと思います。範囲が広い機械ですが、この分野を得意分野にできればかなり勉強時間が短縮できるはずです。
効率的に機械に合格するなら、電気機器を集中的に勉強するべきだと思います。
直流機、誘導機、同期機は分かりにくい
電気機器の分野のなかでも中心になるのは、直流機、誘導機、同期機などです。電験3種の参考書にも説明が書いてありますが、ハッキリ言って分かりづらいです。
管理人もよく分からないまま電験3種に合格してしまいました。実際に選択式の電験3種は、理解が浅くても合格できてしまう試験です。

その後、エネルギー管理士で再度この分野を勉強しましたが、やっぱり分からない…
そこで、オーム社のマンガでわかるシリーズを活用しました。このシリーズは、分かりやすいマンガを交えて、特定の分野を説明しています。これ以上簡単な参考書はないと思います。
直流機、誘導機、同期機を勉強するためにマンガでわかるモーターを今回購入しました。
マンガでわかるシリーズは、マンガのクセに(さすがに失礼かw)非常に細部まで丁寧に説明してくれます。漫画以外の文章部分にも大事なことが書かれており、すべてが漫画で勉強できるというわけでもありません。
昔の管理人のように直流機、誘導機、同期機の分野がさっぱり理解できない人は、この本でさわりや概要を学んでもいいかもしれません。
機械の電気機器の勉強法
教科書>参考書
電気書院の「これだけ機械」は名著と言われています。ただ、電気機器の分野に関しては、実教出版の「工業391 電気機器」という工業高校電気科向けの教科書の方が数倍詳しいし、分かりやすかったです。
写真は工業112ですが、2018年に新訂されました。
直流機の分野で比べてみても、実教出版の教科書の方がこれだけ機械より内容が2倍くらいあります。教科書なので、図もふんだんに使ってあります。
章末に掲載されている問題も質は良さげでしたが、解説がありませんでした。知り合いに高校の先生がいれば、解説付きの先生用教科書を入手できる可能性があります。私は解説付きの教科書がどうしても欲しくて、出版社にまで問い合わせましたがダメでした。
新訂版は答えがついているかどうかすら分かりません。詳しく知りたい方は出版社に問い合わせてみてください。
電気機器の参考書として使うなら、実教出版の「電気機器」はおすすめです。値段も安く、2000円程度で買えます。
購入リンクは参照のためです。
一番安く買うのはお近くの教科書が売っている本屋で購入する方法です。
実教出版以外にも電気系の教科書を発売している出版社はあります。教科書なので、どの出版社のものも非常に分かりやすいと思います。
私は機械科目でしか教科書を使用しませんでしたが、興味がある方は他の科目でも活用しても良いかもしれません。
電気機器の分野に関しては、教科書を使った学習が一番です。
電験3種で教科書を使用するメリット
電験3種という試験は、数学の試験とも言われます。多くの問題が計算問題で、合否を分けるのは受験者の数学力だからです。しかし、電験3種で最も難しいのは、文章問題(論説問題)だと管理人は思います。

その文章問題の対策に教科書が役に立つのです。電験3種で出題される文章問題の知識は、ほとんどが市販の電験3種の参考書にのっていません。そこで、市販の参考書より詳しい教科書の出番となります。
特に文章問題が難しいのが機械科目です。理論や電力の文章問題は、知識問題が多いです。法規は、条文を知っているかどうかが大きいです。
一方で機械の文章問題は「理解」も要求されます。機械に関しては、参考書より内容が詳しい教科書を読み込んで、理解を深めるという戦術が非常にマッチしているのです。
管理人は機械以外の科目は、市販の参考書で十分でした。機械以外の科目が難しく感じる受験者もいると思います。その場合、電子回路や電力などいろいろな種類の教科書があります。
電験3種は工業高校卒業レベルの試験です。つまり、工業高校の教科書を完璧に覚えれば合格できるのです。余談ですが、私の知人は高校の教科書と問題集だけで東京大学に合格しました。それくらい教科書は質が高いのです。
電気機器の基礎の確認
実教出版の「電気機器」演習ノートというものがあります。こちらは、上記の教科書と連動した基礎的な問題集です。教科書を持っていなくても、調べながら解きすすめられます。
基礎知識の穴埋め問題が多く、電気機器の基礎的な知識の確認に役立ちます。新しくなったので中身はよく分かりません。新訂前はよくまとめられていましたが、やはり解説がないのが痛かったです。基礎知識なので、解説がなくてもネットや参考書で補えば活用できます。
購入リンクは参照のためです。
一番安く買うのはお近くの教科書が売っている本屋で購入する方法です。
私はこの演習ノートを1周勉強しました。これをやったから、電験3種の機械の問題が解けるというものではありません。
電験3種という試験自体に確実な勉強方法がないのです。だからどのような形でも、基礎知識を積み重ねるしかありません。私はその選択肢の一つとしてこの演習ノートも勉強しました。
機械の最高レベルの参考書
教科書は機械の参考書としては最高レベルです。参考書として使うだけなら、安い工業高校用の教科書を注文すべきです。
最難関と言われる機械ですが、電気機器の分野を極めれば高確率で合格できるはずです。私は背水の陣で機械を受験したので、できることはすべてやりました。
どうしても機械に受かりたい方は、この勉強法も選択肢に加えてみてはいかがでしょうか?