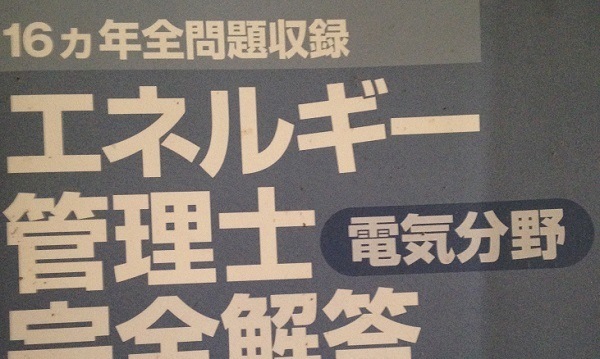なぜ電験3種が難しいかと言うと、過去問だけでは合格できないからと言われます。電気工事士の試験では、過去問の数値を変えただけの問題をよく見ます。電験3種では、過去問と同じ問題はまず出ません。過去問と似た問題がたまに出るくらいです。では過去問を勉強する必要がないのか?というと私は違うと思います。
電験3種の勉強の基本となるのは過去問だと言い切れます。
過去問の勉強
電験3種は過去問の丸暗記は通用しない
過去問だけで受からないというのは、過去問の解き方を機械的に暗記しただけでは受からないという意味です。電験3種の過去問を勉強する場合は、解き方を覚えるだけではダメです。
電験3種の問題は、必ずひねりを入れてきます。生半可な暗記だけでは対応できません。私の知り合いも過去問だけ勉強して受験しましたが、1教科も受からなかったそうです。
理系の方ですと、過去問だけで合格できる人はいると思います。それ以外の方は、参考書で勉強してから過去問の勉強をするという方法が必須になると思います。
過去問を勉強する前に
まず過去問を勉強する前に、過去問の解説がある程度理解できる必要があります。そのための基礎知識がない人に必要なのが参考書です。
参考書は個人個人合う合わないがあるので、どれが良いとは言えません。強いてあげるなら、「これだけ~」シリーズがおすすめです。

上の画像は、実際私が使ったなかから選んだ各科目のおすすめ参考書です。
電験3種の勉強を始める場合、9割以上の受験者は、理論から勉強することになります。

理論の勉強の前に数学の勉強が必要な人は、数学の参考書も必要になるかと思います。
参考書は、私のように1科目に何冊も用意する必要はありません。私はどうしても合格したくて、何冊も参考書を勉強しました。それで合格の確率をあげられるとは思いますが、そこまでしなくても合格できると思います。
1教科に対して最低1冊の勉強しやすい参考書を用意しましょう。そして、過去問の勉強をする前に、参考書を勉強しましょう。参考書や過去問は、繰り返し勉強することが基本です。
過去問の解説を理解する
参考書を繰り返し勉強し、ある程度基礎知識がついたら過去問の勉強を開始します。過去問や参考書の問題を勉強する時は、解説に書いてある事を一字一句理解できるまで繰り返し勉強するべきです。
参考書で勉強を始めたばかりですと、いきなり過去問の解説を理解するのは無理だと思います。しかし、参考書で勉強してから過去問の演習をすれば、最初は難しく感じた過去問の解説も理解できるはずです。
なかには理解できない問題もあると思います。それでも私は必至で理解しようと考えたり、徹底的に調べたりしました。そういう積み重ねで電験3種の基礎知識を磨きました。
分からない言葉は調べる
私は少しでも解説で分からない事があったら、検索エンジンで徹底的に調べました。そうすることで少しずつ知識を積み重ねていきました。参考書の勉強でも同じことです。電気的な用語などは、参考書や過去問の解説よりインターネットの方が詳しく書いてある場合が多いです。
電気の用語は分かりにくい言葉が多いです。短絡、地絡、インピーダンス、アドミタンス、サセプタンスなど、勉強開始時は訳の分からない言葉ばかりです。
すべての用語を覚えなくても電験3種には合格できますが、できる限り言葉の意味を調べましょう。最初は調べても、用語の意味が理解できないかもしれません。それでも、勉強を続けていくうちに理解できるようになる場合も多いです。
現状では、言葉の意味を丁寧に教えてくれる参考書はありません。分からない言葉は、検索エンジンで検索するしかないのが現状です。
計算問題は理解暗記
大学の受験数学では、暗記数学という言葉があります。数学は暗記だ!という考え方です。電験の勉強も計算問題に関しては、基本はそれと同じだと思います。
電験3種レベルの勉強で、電気数学のなんたるかを理解できる人は少ないと思います。私だってなにも電気数学を分かっていません。ただ解き方を覚えて、何となく理解した気分になって試験に合格しただけです。
計算問題は少し考えて解き方が分からなければ、解説を読みましょう。分からない問題を考え込むより、その時間で解説を見て解き方を覚えた方が効率的です。できる限り多くの解法を理解して覚えることに時間を使うべきです。
答えをすぐ見る代わりに、解説だけはじっくり読みましょう。私は解説が理解できなくても、考えたり調べたりして自分なりに納得できるまで解説とにらめっこしました。
電験3種の計算問題は同じような問題は出ませんが、似た問題がたまに出ます。使う公式は同じでも、問題で与えられる条件や数値の単位が違うという場合も多いです。
電験3種の解法パターンを理解して覚える場合は、解説を詳しく読む必要があります。このパターンだからこの公式に代入!では通用しません。私の場合は、解説の計算式を見てどうしてその式が使われるのかを常に意識しながら勉強しました。

当時の私は、解説の式の符号や一つの要素にまで意識をして勉強していたようです。
こういう条件が与えられたから、この公式をこういう形で使うという所まで理解して暗記する必要があります。暗記するというよりは、自然と解法パターンが使いこなせるレベルまで反復練習すべきです。機械的に公式に代入!では本番で応用が利きません。
文章問題は知識の積み重ね
文章問題は知識の積み重ねです。今の検索エンジンは素晴らしいです。分からない言葉は必ず検索すべきです。私は丸暗記ではなく、言葉を理解する事に重点を置きました。文章問題だけではなく、計算問題の中で分からない言葉があっても調べるべきだと思います。
法規の数値だけは丸暗記です。法律で決められた数値の背景まで覚える必要はありません。
電気は確立された学問
電気という分野は、ITなどの分野と違ってすでに確立された学問です。ITの分野ですと毎年新しい技術が出てきますが、電気は違います。新しいモーターが開発されたりしますが、基本となる電気理論は変わりません。その基本の電気理論を勉強するのが電験です。
電験の勉強では、昔から変わることのない電気の基本を勉強します。なので、過去に出題された問題を勉強するのは非常に理にかなっているのです。
毎年試験後に「今年は新傾向の問題が出題された」とつぶやく受験生が多いです。でも、その「新傾向」の問題って全体の何割ですか?
出題された多くの問題を見ると、問われている内容は過去問とあまり変わらないのです。解き方を変えたり、問題を複雑にして難しく見せているだけです。過去問をしっかり理解しながら勉強すれば、対応できる問題が多いと思います。
結局、電験3種の勉強では、過去問を勉強するのが合格への一番の近道だと思います。
おすすめの過去問
過去問は解説が詳しいものを
過去問を選ぶ時の基準は解説の詳しさです。おすすめは電気書院の過去問題集です。4教科過去10年分掲載されているものは、非常に解説が詳しいです。左側ページに問題、右側ページに解説が載っており非常に勉強しやすいです。
ウェブページにもたくさん過去問や詳しい解説があります。
電気書院さんのページにもたくさん過去問が載っています。
参考にしてみてください。
量をこなしたい人は、電気書院の15年分の過去問も悪い選択ではないと思います。15年分の過去問は1教科ずつの過去問が4教科分必要なので、コストパフォーマンスは悪いです。また、テーマ別の過去問になっていますので、本番形式で過去問演習をしたい方には不向きです。
昔の過去問
私はもっと昔の過去問がやりたくて、昔出版された過去問を買いました。結論から言うと、昔の過去問は、そこまで勉強する価値はありません。他にやることがなければ、解いてみてもいいかもしれません。
電験3種が記述式の時代は知りませんが、2000年代前半より昔の過去問は難易度が低いです。第一種電気工事士の問題に毛が生えた程度の問題も少なくありません。
結論
私は勉強の量を重視して、参考書や過去問の量をこなしました。量をこなす事で合格する確率はあげられます。
頭の良い人は合格するだけなら、私のように量をこなす必要はありません。1教科ごとに1冊の参考書を繰り返し勉強し、解説の詳しい過去問を10年分以上勉強すれば、合格ラインに乗ると思います。
自分の能力に自信がない人は1000時間単位の繰り返し勉強が必要です。
どの様な勉強をするとしても、基本は過去問になります。過去問の機械的な丸暗記がダメなのであって、過去問の解説を理解し、パターンを暗記する勉強法なら通用するはずです。