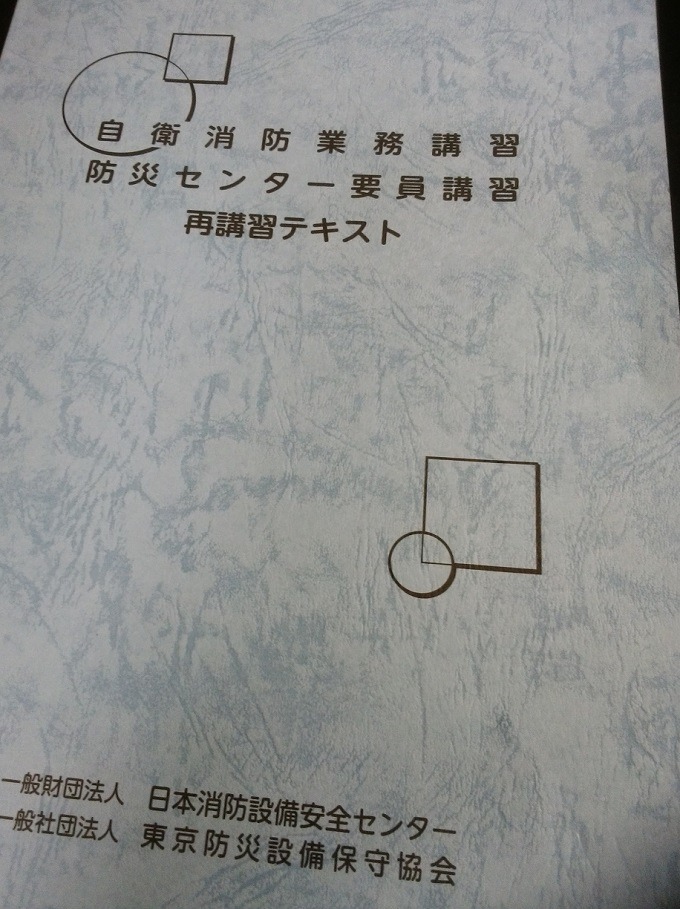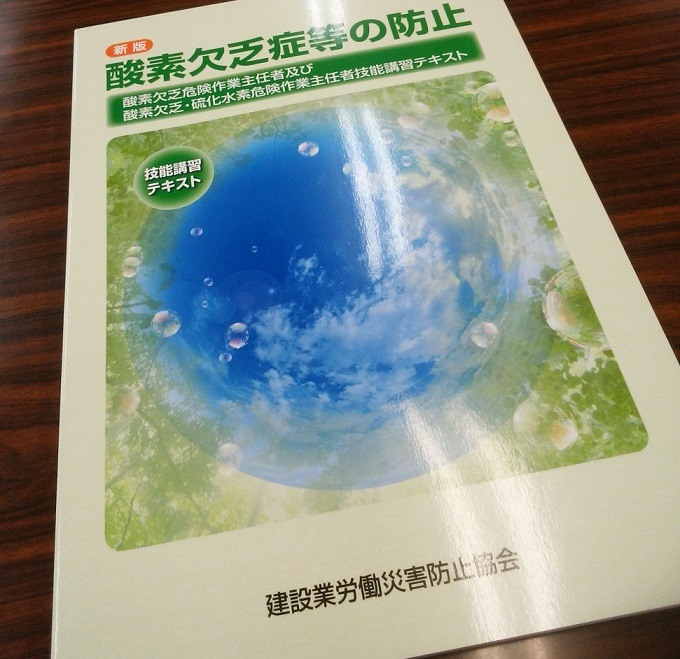最近かなり難しくなった電験3種。すべてを理解して合格すると、電験2種レベルと言われたりもします。しかし、電験3種に合格するだけなら、そこまで難しくないと思います。

一人歩きする電験3種の難易度
電験3種は確かに難しいです。管理人は電験3種を受験してみて、難易度の高さに驚きました。そして、このブログでも電験3種の難易度は過少評価されていると主張してきました。
しかし、今度は過大評価気味かなと感じるようになりました。確かに試験の内容は難関なのですが、合格するだけならそこまで難しい試験ではないと思います。
内容をほぼ理解して合格しようとすると偏差値60くらいの資格ですが、合格するだけなら偏差値55程度の試験だと思います。受験者救済制度のようなものもあるので、偏差値50程度でも合格できる資格だと思います(偏差値は管理人の主観です)。
平均的な学力があれば努力次第で合格できる資格だと思います。その理由は、合格点、科目合格制度、年度ごとに変わる難易度にあります。
合格点は60点以下、55点取ればほぼ合格!
電験3種の勉強をしていると、難しくて頭痛がする人も多いと思います。受験当時、管理人も理解できなくて途中で投げ出したくなりました。
でも少し待ってください。電験3種は60点取ると合格できます。最近では、試験が難しいこともあってか、55点取ればほぼ合格できます。
55点と言うと、半分より1問でも多く正解できれば合格です。しかもマークシート式なので、まったく分からない問題でも正解を拾える可能性があります。
いろいろな資格試験を受験すると分かりますが、マークシート式で半分正解するのは意外と簡単です。逆に5択のマークシートで、真面目に勉強してゼロ点を取る方が難しいです。電験3種は、問題を理解できなくても数割は正解できる人が多いと思います。
実際に真面目に勉強して不合格になった方は、40点台や30点台が多い印象です。40点台なら、あと数問正解すれば合格点です。記述式の試験なら難しいですが、5択のマークシート式なら絶望するような点数ではないはずです。
電験3種は点数を競う試験ではありません。55点で合格しても90点で合格しても、合格は合格です。
5択のマークシート式ということを考えると、4割くらい実力で正解できれば、十分合格点が見えてくる試験だと思います。
それだと科目合格しかできないと言われるかもしれません。それでも、電験3種には科目合格制度があります。
科目合格制度という救済措置
電験3種に合格するのが意外と難しくない二つめの理由は、科目合格制度です。

電験3種は、理論・電力・機械・法規の4科目です。電験には科目合格という制度があり、1度合格した科目は以降2年間免除されます。
その間に4科目すべてに合格すれば、晴れて免状取得です。ただし、どうしても一つだけ受からない科目があったりすると…永遠に合格できません。当然ですね。
例えば、今年理論に合格したとします。来年と再来年は理論を受験せずにすみます。その間に残り3科目を合格すれば良いのですが、合格できないとその次の受験で理論が復活します。
管理人もこの科目合格制度を利用して合格しました。
【管理人の場合】
| 年度 | 理論 | 電力 | 機械 | 法規 |
| 1年目 | 合格◎ | 欠席× | 欠席× | 合格◎ |
| 2年目 | 免除○ | 合格◎ | 合格◎ | 免除○ |
| 電験3種合格!! | ||||
電験3種を4科目すべてに1年で一発合格する人は、受験生の1%程度と言われます。100人に1人ですね。
科目合格制度がなければ、電験3種は難関試験です。しかし、科目合格制度があれば、勉強時間がとれない人でも複数年計画で合格できます。
1年目は理論と法規にしぼって勉強し、2年目は電力と機械にしぼって勉強するという戦略が使えます。管理人的には、1年目から4科目すべてを勉強した方が良いと思います。ただ、時間がない人は、集中して特定の科目を勉強するのも良いと思います。
そしてこの科目合格制度があることで、運が良ければ勉強量や実力が足りなくても電験3種に合格できます。
年度ごとに変わる難易度
電験3種は、年度ごとに科目の難易度が変わります。ある年は、理論が難しい。その次の年は、機械が難しいという具合です。
そしてこの逆もあります。
ある年は、理論が簡単。ある年は、機械が簡単という具合です。年度ごとの難易度の差ならどの資格試験にも多少はありますが、電験3種は難易度の年度ごとの差が激しいのです。
合格率でみる難易度
例えば平成28年は、機械がものすごく簡単でした。前年の平成27年は、法規が簡単でした。平成26年は、電力が簡単でした。
合格率でみると、
平成28年の機械の合格率が、24.3%。平成27年は、10.7%。
平成28年の法規の合格率が、14.2%。平成27年は、20.0%。
平成28年の電力の合格率が、12.4%。平成26年は、21.2%。
合格率だと少し分かりにくいかもしれませんが、合格率の年度ごとの差が激しいのは分かると思います。
管理人の感覚ですと、合格率が20%台の試験は普通より少し難しいくらいの難易度です。合格率が10%台に入ると難しさがぐっと上がるイメージです。合格率が一桁%になると、明らかに難関だと思います。
簡単な科目を確実に拾おう
平成26年~平成28年の間にその年の簡単な科目に合格していけば、3年間で電力、機械、法規の3科目に合格できます。残りの理論をどこかの年で合格しておけば電験3種に合格できます。
そして、簡単な年度でも、合格点が60点未満の場合が多いです。
電験3種の法則としては、前年に難しかった科目が翌年は比較的簡単な場合が多いです。平成28年に簡単だった機械は、前年の平成27年は難しかったです。
当ブログの記事でも、平成28年の機械が易しくなる可能性があると予想していました。
もちろん数年連続で特定の科目が難しい場合もありますが、難易度がずっと高いままといったことはまずありません。必ずどこかの年度で受験者救済(?)があります。
難易度が低い科目を確実に拾うために、1年目から4科目すべてを勉強した方が良いのです。運が良ければ、難易度の低い科目を拾い続けて電験3種に合格できます。
科目合格制度の使い方としては、二点あります。集中的に特定科目を勉強するのが一点。難易度の低い科目を拾うのがもう一点です。
年度ごとの難易度の差が激しいことと科目合格制度があることで、電験3種はかなり合格しやすくなっています。
最後に
電験3種は難しいですが、努力で合格できる試験だと思います。試験内容は受験者を不合格にさせるための試験ですが、試験制度は受験者を合格させるための試験です。
電験3種の試験や制度の癖をうまく理解して、戦略を立ててみてください。時間はかかるかもしれませんが、合格を勝ち取るのはそこまで難しくありません。