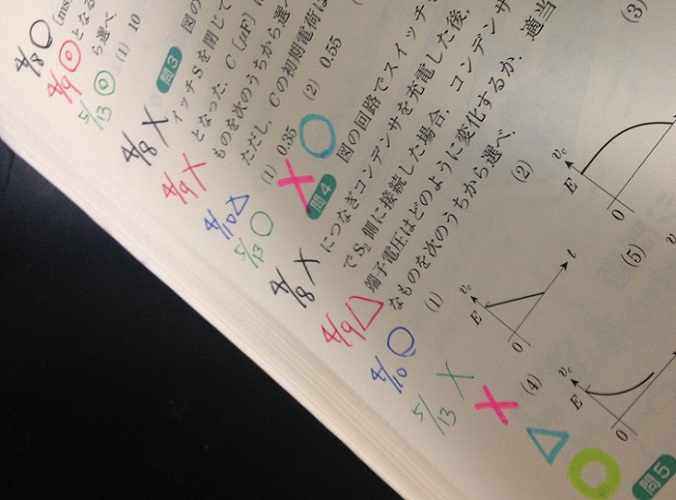電験3種のなかで最も素直な科目は電力だと思います。他の科目に比べて電力は、普通の人でも内容がイメージしやすいはずです。この記事では、電験3種の電力科目の難易度、参考書、勉強方法を紹介ていきます。
【受験概要】
【科目名称】電力(第3種電気主任技術者)
【受験年度】平成25年度
【自己採点】85点
勉強時間
期間は1年間、勉強時間は250時間。
受験前年の平成24年度に理論と法規を合格していました。理論で電験3種の基礎は学習済みでした。法規の計算問題も電力とかぶるところがあると思います。
スタート地点はかなり有利な状態でした。そこから250時間の勉強時間は多過ぎだと思います。試験当日も電力は絶対落ちないなと感じていました。
ゼロから電力だけ勉強しても、200時間も勉強すれば十分勝負になると思います。
受験時の主な所有資格:第2種電気工事士
【難易度】
電験三種 ★★★★★★★★☆☆ (8/10 難関中位)
電力科目 ★★★★★★☆☆☆☆ (6/10 普通上位)
電力の過去の合格率
| 受験年度 | 合格率 |
| 平成22年 | 12.7% |
| 平成23年 | 14.5% |
| 平成24年 | 24.8% |
| 平成25年 | 12.4% |
| 平成26年 | 21.2% |
| 平成27年 | 19.5% |
| 平成28年 | 12.4% |
| 平成29年 | 13.6% |
| 平成30年 | 25.1% |
| 令和元年 | 18.3% |
| 令和2年 | 17.7% |
電力は計算問題と文章問題の比率が5:5~4:6くらいでしょうか。文章問題のほうが少し多いです。計算問題が多い順に、理論>機械>電力>法規 となっています。
最近は、電力も難しい年が多くなってきています。簡単な年と難しい年の差が激しくなっている印象です。
管理人が合格した平成25年度も「電力が難しかった」試験回でしたが、特に難しさは感じませんでした。なぜなら出題された内容がほとんど参考書にのっていたからです。下にあげた参考書を隅まで勉強すれば、電力は攻略できると思います。
電力科目の特徴
電力では、実務に近い知識が問われます。機械の中身や動作が問われる機械科目に対して、機械の役割を問われるのが電力です。
発電機の仕組みを問うのが機械。発電機の役割を問うのが電力です。
普通の人は、発電機の仕組みなど気にしませんし、中身も見ません。でも、発電所が運転しているのは見たことがある人が多いと思います。福島原発が話題になったので、発電に関して調べてみたという人もいるかと思います。このような点が電力の勉強のしやすさやイメージのしやすさにつながっているのだと思います。
電力は勉強量に比例して点数が伸びると思います。複雑なものを理解したり、無機質な暗記を要求されることが少ないからです。最も勉強しやすく、勉強した人にとって最も合格しやすい科目が電力だと思います。
【参考書】
(1)これだけ電力
電力に関しては、どの参考書を選んでも大差ないかと思います。4科目で1冊になってる参考書だけはおすすめしません。これだけ電力は図が多く、文字も大きくて読みやすさではトップクラスです。これだけシリーズは全科目購入しましたが、法規以外はおすすめです。
(2)完全マスター 電力
非常に詳しい参考書です。式の導出などの細かい部分も書いてあります。書いてあることすべてを理解しようとすると3種レベルを超えます。とにかく詳しい参考書で勉強したいという人におすすめです。それ以外の人は他の参考書で勉強するほうが無難です。
文字の大きさも小さく、漫画風の挿絵などもありません。非常に堅いイメージの参考書です。一般の人から見ると参考書というより専門書に見えるかもしれません。
(3)徹底解説テキスト 電力
簡単な例題を数多く解きながら学習をすすめていく参考書です。問題を解きながら理解を深めていくという勉強法に合った参考書です。ゴロ合わせがよく載っていますが、必要性があるのかかなり疑問です。それ以外は非常に使いやすい参考書だと思います。
(4)マンガでわかる発電・送配電
電験3種の電力科目のさわりを誰にでも分かりやすく説明している参考書です。難しい参考書を読んでばかりで、イマイチ内容が理解できてるか心配だという人におすすめです。
マンガでわかるシリーズは、親しみやすいマンガという形でありながら、非常に細部まで丁寧に説明してくれます。また、漫画以外の文章部分にも大事なことが書かれており、すべてが漫画で勉強できるというわけでもありません。
この本だけで勉強しても、電験3種の電力の問題は解けません。サブ的な読み物や理解を深めるための参考書としては非常に役に立つと思います。
【勉強方法】
実務の経験がない人は、とにかく分からない言葉が多いと思います。
分からない言葉を一つずつ参考書や検索エンジンで調べましょう。用語をただ覚えるのではなく、意味を考えて覚えた方が良いです。
検索では、まず分からない言葉をgoogleで検索して調べます。そしてその言葉を今度は画像検索します。参考書以外の知識を増やすことで、知識のイメージを膨らませていきましょう。
参考書を勉強するのは当たり前です。過去問と同じ問題がほとんど出題されない電験では、参考書だけの勉強では限界があります。特に用語の多い電力では、検索エンジンの活用がキーになると思います。
見慣れない単語があったら、参考書を読んで検索もするという癖をつけると良いと思います。
電力は文章問題が6割程度なので、暗記が必要な分野が多いです。管理人は簡単な単語カードを作っての勉強も取り入れました。その単語カードに興味がある方は、下の記事からどうぞ。

言葉の意味を考える
すべての資格勉強に言えることですが、用語を覚えるときは言葉そのものの意味を考えると覚えやすいです。
例えば、サージタンクという言葉であれば、surgeするtankです。サージ[surge]とは急上昇や急増加するという意味です。急に増えた液体を蓄えるタンクがサージタンクです。こうすることでサージ電流と言われてもイメージできると思いますので、応用の幅が広がります。
ちなみにサージ電流は、急上昇する電流という意味です。
最後は過去問で仕上げ
当たり前のことですが、参考書の勉強が終わったら過去問の演習をしましょう。電験3種は過去問と同じ問題は出題されないですが、過去問演習が勉強の中心だと思います。大学電気科卒の人の場合、法規以外は過去問演習だけで合格できるのかもしれませんね。
過去問は上が4教科の10年間分の過去問が1冊に掲載されているもの。通称電話帳です。左1ページに問題が1問、その問題の解説に右1ページをまるまる使っています。非常に勉強しやすいです。下は、電力1科目だけの15年間分のテーマ別過去問です。
11~15 年前というと2000年台半ばです。その頃は電験3種が簡単でした。その頃の過去問も演習する価値はあると思いますが、過去問を4教科分購入しなくてはな りません。徹底的に対策したい方は15年間の過去問。あまりお金をかけたくない方は10年分でいいと思います。

【最後に】
管理人は、電力が一番勉強しやすかったです。法規のほうが勉強時間は少なくて済みますが、条文や数値など無機質な暗記が多いです。電力も暗記はありますが、関連性などを理解しながら暗記すると勉強しやすいです。
電力は、パソコンを利用した時間が一番多かった科目でした。図書館にノートPCを持ち込んで、検索エンジンを開きながら勉強したりしました。電験3種は参考書だけでは合格が難しい試験です。ぜひ検索エンジンも活用してみてください。
電力に関しては、数年おきに易しい年があります。非常に勉強しやすい科目ですので、科目合格を狙う人にもおすすめの科目です。