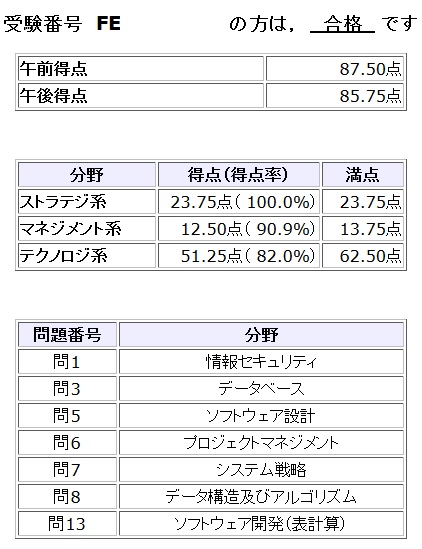難易度が高いと言われる第3種電気主任技術者試験。「電気工事士と電験はレベルが違う」、「過去問だけでは合格不可能」、「公式を覚えるだけでは合格できない」などいろいろと言われています。この記事では、電験3種がなぜ難しいのかを全力で考えてみようと思います。

最初の難関は交流を理解すること
「家庭用の電圧って100Vでしょ?」と問われれば、「正解です」と答えます。でも、交流なので常に100Vというわけではありません。
この考え方が最初は理解できませんでした。
電気工事士の試験でも交流を扱いますが、交流を交流と扱わなくても合格できてしまいます。電気工事士では交流電圧が実効値で与えられるので、これを直流の電圧と同じようにとらえてオームの法則 (V=IR) に適用すればほとんどの問題が解けます。
これが不幸の始まりです。

交流には位相があります。電験3種では位相を意識しないと解けない問題が多いです。「電圧は100Vって書いてんだから、常に電圧は100Vだろ!」←この考え方が電験3種では通用しないのです。
この交流の概念を理解することが、電気工事士から電験へのステップアップで一番難しい点ではないでしょうか?
交流の勉強は電気数学の基礎から
多くの電験3種の理論の参考書では、交流の前に直流を学びます。直流回路の問題から勉強するので、それと同じ感覚で交流の問題を解き始めます。そして交流の概念が理解できず、本人は何が理解できないのかイマイチ分からずに挫折するパターンも多いと思います。
もしくは理解が中途半端なまま勉強を進めて、最終的に挫折するというパターンもあるのかなと推測します。これらの不幸なパターンは、電気数学の基礎から勉強すれば避けられる場合が多いと思います。
電験3種は過去問だけでは合格できない?
電験3種は過去問だけで合格できる試験です。
ただし、頭の良い人と電気専攻の人に限ります。※最近の試験では、これらの人も法規だけは参考書で勉強する必要がありそうです。
普通の人も過去問を勉強するのが一番効率的な方法ですが、過去問だけではなかなか合格できないと思います。

一つ例を挙げてみようと思います。
下の公式は、電力科目の水車の理論出力を求める公式です。
![]()
よく試験に出る分野ですが、
流量
で有効落差
で運転している時の水車発電機の出力
を求めよ。
こんな感じの公式に数字をあてはめるだけの問題は、まず出題されないでしょう。
平成27年度の電力の問1にこの分野が出題されました。問題文に、![]() という公式と、重力加速度
という公式と、重力加速度![]() 、水の密度
、水の密度![]() が与えられた穴埋め問題でした。
が与えられた穴埋め問題でした。
多くの参考書で太字になっている![]() という公式の意味を問う良問です。
という公式の意味を問う良問です。![]() と呪文のように暗記してきた受験生を、問1からいきなり振るい落としにかかる問題です。
と呪文のように暗記してきた受験生を、問1からいきなり振るい落としにかかる問題です。
実際の本試験でも、このような問題が手を変え品を変え出題されます。過去問の解き方だけ覚えても、過去問とまるっきり同じ切り口からはあまり出題されません。過去問だけでは合格できないというのは、過去問を暗記しただけでは合格できないという意味です。
普通の人には、参考書で基礎を学ぶというプロセスがどうしても必要になるのです。

参考書の勉強により基礎を積み重ねることで、自然と応用力もつきますし、問題を解く速度もあがります。そうなれば、本番で少しひねった問題が出ても、自分で考えることができるようになります。
ちなみに平成27年度電力の問1は、下の記事のような強引な考え方で簡単に解けます。

公式を覚えるだけでは合格できない?
電験3種の公式は覚えるものだと思います。しかし、ただ公式を覚えているだけでは使いものになりません。
例えば、機械科目に誘導電動機の同期速度の公式があります。
![]()
この公式も大抵の参考書に太字で出てきます。
では、
定格周波数f=50[Hz]、p=4極の三相かご形誘導電動機の同期速度N[rad/s]を求めよ。
同期速度を求めるこの問題を解けますか?
管理人は、この問題が初見では解けませんでした。
![]()
では不正解です。
正解は、
![]()
になります。
![]() という公式は、[min-1]が単位の同期速度を求める公式です。今回の問題では、[rad/s]が単位の同期速度を求めなくてはなりません。
という公式は、[min-1]が単位の同期速度を求める公式です。今回の問題では、[rad/s]が単位の同期速度を求めなくてはなりません。
![]() という公式は、
という公式は、![]() ということなのです。1分間に何回転したかを求める公式です。
ということなのです。1分間に何回転したかを求める公式です。
同じ要領で[rad/s]が単位の同期速度を求める公式を考えてみると、![]() となるのです。こちらは1秒間にどれくらいの角度を進んだかを求める公式です。
となるのです。こちらは1秒間にどれくらいの角度を進んだかを求める公式です。
同じ同期速度を求めるにしても、単位が違うだけで公式が大きく違います。こんな公式をすべて覚えてられませんよね。というか、参考書にこんな公式はのっていないはずです。これが公式をただ単に覚えるだけでは電験3種に合格できない理由です。
この手の公式の変換がスムーズにできる人は、電験3種に合格できる人だと思います。管理人はぎりぎりで3種に合格したので、エネルギー管理士の勉強でもこういう問題が解けませんでした。
公式は暗記すべきだが…
参考書にのっている公式は暗記すべきです。しかし、暗記した公式だけでは問題が解けない場合も少なくないです。
暗記した公式を変換して、変換して、変換して…
簡単な人には簡単なのかもしれません。逆にいくら頑張っても電験3種に合格できない人がいるのも納得できます。センスの差と言えばそれまでです。
公式を覚える時は、公式の意味を考えながら覚えた方が応用問題にも対応できるようになります。オームの法則も、「Vが電圧で、Iが電流で、Rが抵抗」という風に覚えているはずです。
他の公式も、なるべく公式の数字やアルファベットの意味を考えるべきです。ただ単に覚えるのではなく、正確に細かいところまで意味を把握しましょう。しかし、電験3種レベルでは、覚えることでしか対応できない公式も存在するのが難しいところです。
最後に
管理人の足りない脳みそをフル活用して、電験3種の難しさについて書いてみました。詳しい人から見れば間違ったことがあるかもしれませんが、笑って許してやってください。
電験3種という試験は、努力で合格できる試験と言われます。管理人も根性で約1000時間勉強して合格しました。
人によっては、合格まで2000時間かかっても不思議ではない試験です。その難易度の高さは、暗記力ではなく思考力が要求されるからだと思います。応用力や思考力に自信がない場合は、管理人のように長時間勉強して解法パターンを理解して暗記しまくるしかありません。
年々電験3種が難しくなっている気がします。とにかく過去問外しの問題が増えて、さらに思考力や応用力が問われるようになっています。「3種」でここまで難しい試験って他にあるのでしょうか?